はじめに
「最近、おばあちゃんが同じ話を何度も繰り返すのよ。前はそんなことなかったのに…」
介護の現場や家族から、そんな声を耳にすることは少なくありません。私が関わったあるご家庭でも、最初は「年のせいかな」と軽く考えていたそうです。ところが、財布をどこに置いたか忘れて探し回ったり、料理の味つけを間違えることが増え、家族が不安を抱くようになりました。
認知症は早期に気づき、医療や介護のサポートにつなげることがとても大切です。しかし「病院に行くほどではないのでは」と迷うご家族も多いのが現実です。そんなときに役立つのが、自宅でできる セルフチェックリスト です。
この記事では、介護関係者やご家族が在宅で使える認知症セルフチェックのポイントを、分かりやすくまとめました。日々の暮らしの中で「小さなサイン」に気づけるようになることを目的にしています。
1. なぜセルフチェックが大切なのか

認知症は、進行性の病気です。しかし早期に気づき、医師の診断やサポートを受けることで、生活の質を保ちながら過ごせる期間を長くすることができます。
とくに初期段階では「物忘れが多いだけ」「年齢のせい」と思われがちです。そのため受診が遅れてしまうことが少なくありません。
早期発見が大切な理由は以下のとおりです。
- 治療薬の効果を発揮できるのは、早期の段階であることが多い
- リハビリや生活習慣の工夫によって進行をゆるやかにできる
- ご本人が自分の意思で将来の生活を考え、準備できる時間を持てる
- 家族が介護の体制や支援サービスを早めに整えられる
- 本人・家族ともに「安心材料」を得て、不安を軽減できる
セルフチェックリストは、あくまでも 「気づきのきっかけ」 にすぎません。診断を確定するものではありませんが、日常で感じる違和感を整理するのに役立ちます。
2. 在宅で使えるセルフチェックリスト
ここでは、厚生労働省や認知症関連学会が公表している情報をもとに、家庭で確認できる代表的なチェック項目を紹介します。印刷して利用できるように、チェック欄をつけています。
(1)記憶に関するサイン
□ 同じことを何度も尋ねる
□ ついさっきの会話や出来事を思い出せない
□ 大切な物をどこに置いたか忘れることが増える
□ 予定を忘れて約束を守れない
(2)判断力や理解力に関するサイン
□ 買い物でお金の計算に時間がかかる
□ 知っている道で迷うことがある
□ 新しいことを覚えるのが極端に苦手になった
□ 説明を聞いても理解するのに時間がかかる
(3)生活習慣や行動の変化
□ 洗濯や料理など家事の手順を間違える
□ 身だしなみを気にしなくなる
□ 趣味や好きだったことへの関心が薄れる
□ テレビや新聞の内容を理解できなくなる
(4)気持ちや性格の変化
□ 些細なことで怒りっぽくなる
□ 意欲がなく、家に閉じこもりがちになる
□ 疑い深くなり、家族に対して不信感を持つ
□ 不安や落ち込みが強くなる
3. チェックリストの使い方
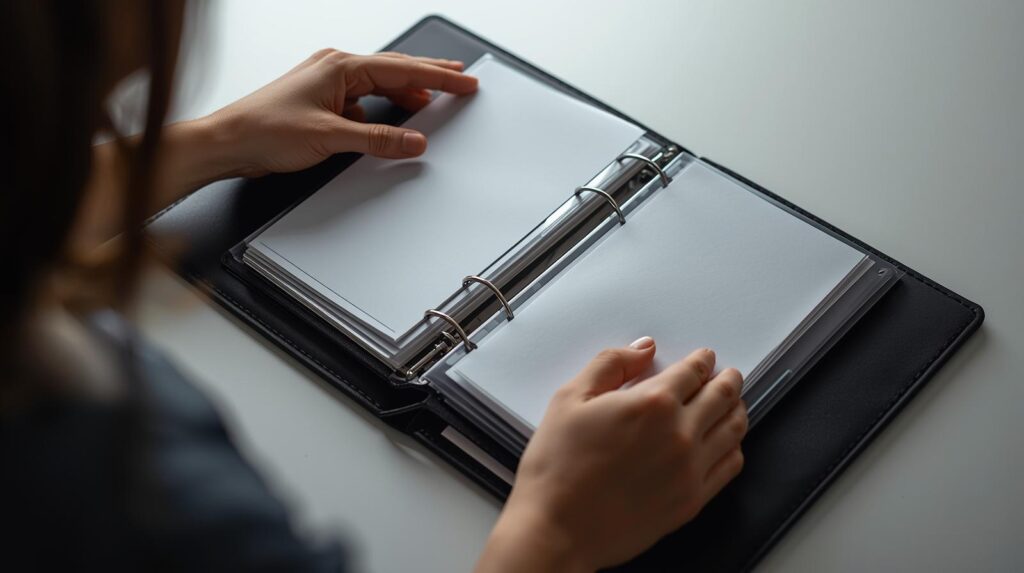
セルフチェックを行う際には、以下のポイントを押さえてください。
- 本人と家族の両方の視点で確認する
本人は「まだ大丈夫」と思っていても、家族から見ると変化が明らかなこともあります。 - 一度で判断せず、継続的に観察する
その日の体調や気分によっても、できる・できないが変わることがあります。数週間~数か月単位で様子を見ましょう。 - 結果をそのまま受け止めず、医師に相談する
チェックリストはあくまで「気づき」です。気になる点が多ければ、早めにかかりつけ医や専門医に相談してください。その際、このチェックリストを医師に提示しましょう。
4. 受診につなげる工夫
「病院に行こう」と本人に伝えても、抵抗を示すことは少なくありません。その際には、以下のような工夫が有効です。
- 「健康診断のついでに相談してみよう」と自然に誘う
- 「最近疲れやすそうだから一緒に病院へ行こう」と体調の不安をきっかけにする
- 家族だけで抱え込まず、介護職や地域包括支援センターに相談する
受診を早めることは、ご本人だけでなく介護を担う家族の安心にもつながります。
5. 介護現場からのエピソード
私が訪問したある家庭では、家族が「同じ料理を二度作る」母親の変化を心配していました。最初は「疲れているのかな」と思っていたそうですが、セルフチェックをつけてみると「財布を忘れる」「約束を忘れる」など複数のサインが明らかになりました。
その記録を持って医師に相談した結果、早期のアルツハイマー型認知症と診断されました。治療薬を開始し、リハビリや生活支援を取り入れることで、母親は以前のように笑顔を取り戻しました。家族も「チェックリストがなかったら、もっと遅れていたと思う」と話していました。
6. 家族にできるサポート

セルフチェックで気づいた後、家族ができることもたくさんあります。
- 生活リズムを整える(朝の散歩や食事の時間を決める)
- 栄養バランスのよい食事を一緒に楽しむ
- 認知症カフェや地域活動に参加する
- 本人のプライドを傷つけないような声かけを心がける
こうした小さな積み重ねが、ご本人の安心感や生活の安定につながります。
まとめ
認知症は「気づきの早さ」が、その後の生活を大きく左右します。在宅でのセルフチェックは、その第一歩となる大切なツールです。
ただし、チェックの結果は「診断」ではなく「気づき」であることを忘れずに。気になるサインが見られたときには、医師や専門職に早めに相談してください。
ご本人も家族も「不安を抱え込まないこと」が、認知症と向き合う第一歩だと思います。
出典
- 厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」
- 公益社団法人 認知症の人と家族の会
- 日本認知症学会「認知症の診断・治療・ケアに関するガイドライン」
- 東京都福祉保健局「認知症セルフチェックリスト」



コメント