はじめに
「最近、同じ話を何度もしてしまう」
「予定を忘れてしまうことが増えた」
そんな変化に気づくと、「もしかして認知症では?」という不安が頭をよぎることがあります。
しかし、物忘れのすべてが認知症というわけではありません。
正常な加齢による物忘れと、認知症の中間の段階にあたる「MCI(軽度認知障害)」という状態があります。
このMCIの段階で気づき、生活を見直すことで、進行を防いだり遅らせたりできる可能性があります。
本記事では、MCIと認知症の違い、日常生活での見分け方、そして医療や生活面での具体的な初期対応方法についてお伝えします。
1. MCI(軽度認知障害)とは?
MCI(Mild Cognitive Impairment)は、日本語で「軽度認知障害」と呼ばれます。
これは加齢による物忘れと認知症の中間段階で、次のような特徴があります。
- 記憶力や判断力が少し低下しているが、基本的には自立して生活できる
- 家事や買い物、趣味、金銭管理なども自分でできる
- 会話は成立し、身の回りのこともこなせる
MCIの人のうち、1年で約10〜15%が認知症に進行するといわれています。
一方で、生活習慣の改善などで正常な状態に戻る人もいます。

2. 認知症との違い
認知症は、脳の病気や障害により記憶や判断力が低下し、日常生活に支障が出ている状態を指します。
比較表:MCIと認知症の違い
| 項目 | MCI(軽度認知障害) | 認知症 |
|---|---|---|
| 記憶の低下 | 多少あり(ヒントがあれば思い出せる) | 顕著(ヒントがあっても思い出せない) |
| 日常生活 | ほぼ自立できる | 介助や見守りが必要 |
| 判断力 | 軽度低下 | 明らかな低下 |
| 進行 | 改善する可能性あり | 基本的に進行性 |
| 社会活動 | 継続可能 | 困難になることが多い |
3. 日常生活で見られる「境界線」
違いを見分ける重要なポイントは、**「日常生活に支障が出ているかどうか」**です。
MCIに多い様子
- 予定を忘れるが、メモやカレンダーを見ると思い出せる
- 鍵や財布を時々探すが、思い出して見つけられる
- 新しいことを覚えるのに少し時間がかかる
- 複雑な家事や事務作業で疲れやすくなったが、できる
認知症に多い様子
- 予定を完全に忘れ、思い出すきっかけがあっても思い出せない
- 鍵や財布を冷蔵庫など不自然な場所に置く
- 慣れた道で迷う
- 言葉が出にくく、会話が途切れがち
- 金銭管理や服薬が困難になる
注意点:ご本人には症状の自覚がないことも多く、家族や周囲の人の観察が非常に重要です。
4. MCIを放置するとどうなる?
放置すると、認知症へ進行するリスクが高まります。特にアルツハイマー型認知症は、発症の数年前から脳の変化が始まるため、気づいた時点での対応が大切です。
5. 初期対応のポイント
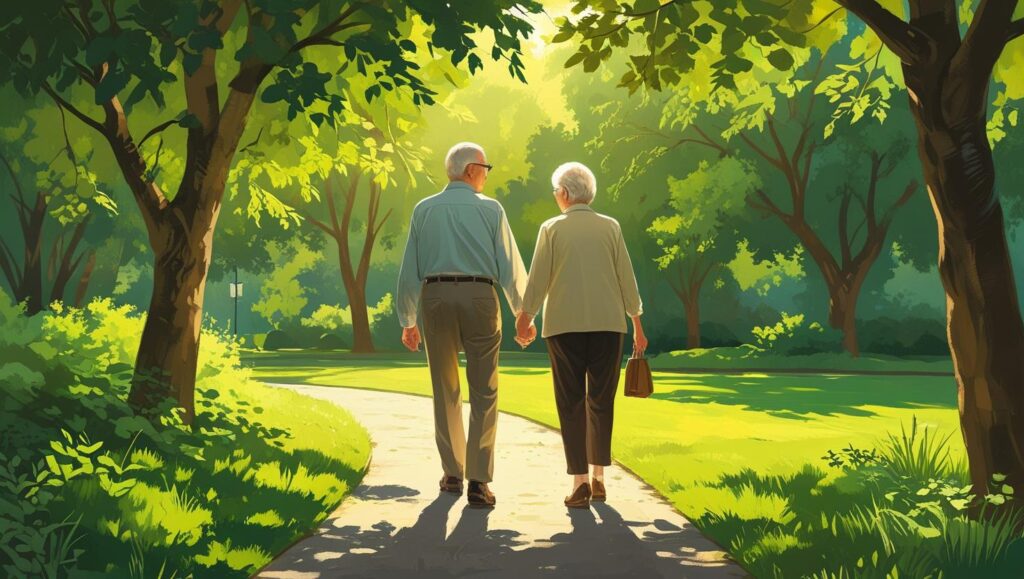
① 早期発見と受診
- 簡易型検査
- 「長谷川式認知症スケール」や「MMSE(ミニメンタルステート検査)」などがあり、病院や地域包括支援センターで受けられます。
- 数分〜10分程度の質問形式で、記憶力や見当識(時間や場所の把握能力)をチェックします。
- 血液検査で他の原因を確認
- 甲状腺機能低下症、ビタミンB12欠乏、葉酸不足、肝疾患や腎疾患、脱水なども物忘れの原因になります。
- これらは治療によって改善できる可能性があります。
② 脳を使う生活習慣
- 読書、日記、計算ドリル、クロスワード、楽器演奏など
- 新しい趣味を始めることが特に効果的(例:英会話、手芸、園芸など)
③ 有酸素運動
- 週150分以上(1日30分×週5日が目安)
- 具体例:ウォーキング、軽いジョギング、サイクリング、エアロビクス、水中ウォーキング、太極拳
- 無理なく続けられるものを選び、友人や家族と一緒に行うと継続しやすいです。
④ 食事(地中海食)
地中海食は、認知症予防に効果があるとされる食事法です。
具体的には:
- 主食はパンやパスタ、玄米などの全粒穀物
- 野菜・果物をたっぷり
- 魚介類(特に青魚)を週2回以上
- オリーブオイルを主要な油として使用
- ナッツ類を適量
- 赤ワインは少量(医師と相談)
- 肉は鶏肉や赤身を控えめに、加工肉は避ける
⑤ 基礎疾患の管理
- 高血圧、糖尿病、脂質異常症などのコントロールは認知症予防にも直結します。
- 定期的な血圧測定、血糖測定、血液検査での脂質チェックが重要です。
- たばこや過剰なアルコールも認知症を進めるリスクです。
⑥ 耳の聞こえもチェック
- 難聴は認知症のリスク因子です。
- 補聴器の使用や耳の検査を受けることで、会話や情報取得の機会が増え、脳への刺激が保たれます。
6. 家族のサポートで大切なこと

- 本人が自覚していないこともあるため、責めずに変化を共有する
- カレンダーやメモを見やすい場所に貼る
- 複雑な説明よりも短く、具体的な指示を
- できたことを積極的に褒める
- 病院受診は「健康チェック」という形で誘う。認知症というキーワードを使うと嫌がられる可能性も考慮して。
- 聴力や視力、持病の管理も一緒にサポートする
まとめ
- MCIは改善の可能性がある段階で、早期発見と生活改善がカギ
- 日常生活に支障があるかどうかがMCIと認知症の境界線
- 医療検査(簡易検査+血液検査)と生活習慣の見直しで進行を遅らせられる
- 家族の観察と温かいサポートが予防と安心につながる
物忘れを「年のせい」と片付けず、気づいたら一歩踏み出すことが、将来の生活を守ります。



コメント