はじめに
「母が認知症と診断されてから、一番心配だったのはお金のことでした。年金や預貯金の管理はもちろん、介護サービスの費用をどう支払っていくのか、将来的に施設へ入所するときに資産をどのように使えばよいのか……。父も高齢で、私が仕事をしながら管理するのは限界がありました。そんなときに市役所で紹介されたのが“成年後見制度”と“家族信託”という制度でした。」
認知症の介護において、身体的なサポートや日常生活の工夫と同じくらい大切なのが「お金の管理」です。認知症が進行すると、本人が契約や資産の判断を適切に行うことが難しくなり、財産の不正利用や生活費の不足といったリスクが高まります。こうした問題を予防し、安心して介護を続けるために、成年後見制度や家族信託といった仕組みを知っておくことはとても重要です。
この記事では、介護関係者やご家族に向けて、成年後見制度と家族信託の仕組み、違い、利用する際の注意点をわかりやすく解説します。
1.認知症とお金の管理の課題
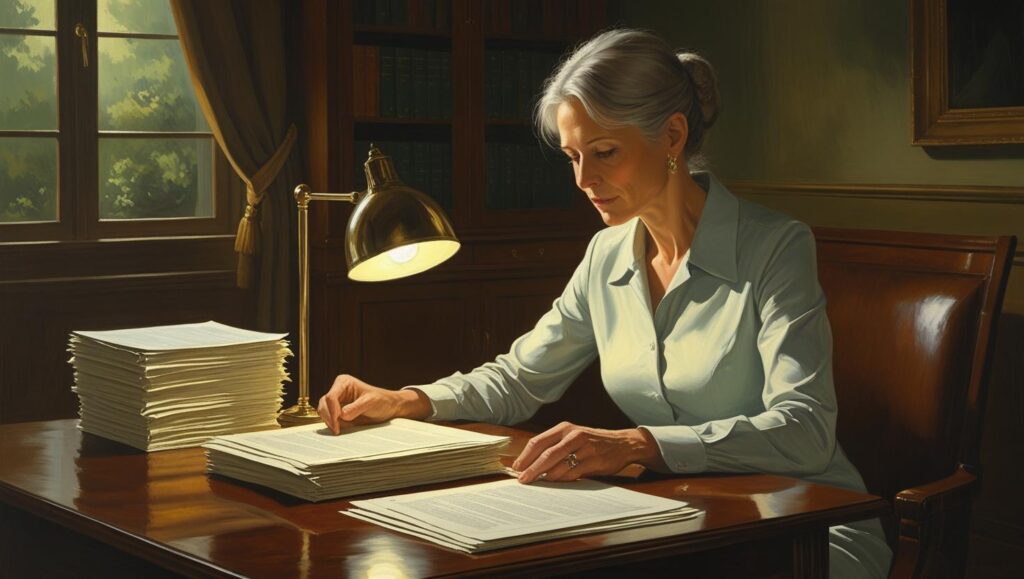
認知症になると、記憶や判断力に影響が出ます。初期の頃は自分でお金の管理ができても、次第に以下のような困りごとが出てきます。
- 通帳やカードを紛失する
- 光熱費や家賃の引き落としを忘れる
- 不要な訪問販売や詐欺に巻き込まれる
- 介護サービスや医療費の支払いを正しく判断できない
- 財産を巡って家族間で意見が対立する
こうしたトラブルを未然に防ぐには、本人の意思を尊重しつつ、法的に支援できる仕組みを整えることが必要です。
2.成年後見制度とは
(1) 制度の概要
成年後見制度は、判断能力が不十分になった人に代わって、家庭裁判所が選任した後見人が財産管理や契約行為を行う仕組みです。
対象は主に認知症、高次脳機能障害、知的障害、精神障害などで判断力に制限がある方です。
(2) 種類
成年後見制度には大きく2種類あります。
- 法定後見制度
認知症などで判断力がすでに低下している場合に利用する。家庭裁判所に申立てを行い、後見人が選任される。
後見人は本人の財産管理や契約手続きを行うが、裁判所の監督を受ける。 - 任意後見制度
本人に判断力があるうちに「任意後見契約」を公正証書で結び、将来に備える仕組み。発効は判断能力が低下したとき。
(3) メリット
- 法律に基づく制度であり信頼性が高い
- 悪質な詐欺や不当な契約から本人を守れる
- 裁判所の監督があるため透明性が確保される
(4) デメリット
- 家庭裁判所への申立てが必要で手続きが煩雑
- 費用がかかる(申立てに数万円、後見人報酬も月1~2万円程度)
- 一度開始すると簡単にやめられない
- 財産運用や柔軟な資産活用が難しい場合がある
3.家族信託とは

(1) 制度の概要
家族信託とは、財産を「信頼できる家族(受託者)」に託し、その家族が本人(委託者)のために管理・運用する仕組みです。近年、認知症対策として注目されています。
(2) 特徴
- 契約によって柔軟に内容を決められる
- 財産の名義を受託者に移すため、本人の判断力が低下しても運用を継続できる
- 裁判所の関与は基本的にない
(3) メリット
- 財産管理を柔軟に設計できる
- 任意後見よりも実際の運用に強い
- 相続対策や事業承継にも応用できる
(4) デメリット
- 専門的な知識が必要で契約内容を慎重に設計する必要がある
- 裁判所の監督がないため、不正利用のリスクがゼロではない
- 専門家に依頼する場合の初期費用が数十万円かかることもある
4.成年後見制度と家族信託の違い
| 項目 | 成年後見制度 | 家族信託 |
|---|---|---|
| 主体 | 裁判所の選任による後見人 | 家族などが受託者となる |
| 利用開始 | 判断能力が低下してから | 判断能力があるうちに契約 |
| 監督 | 家庭裁判所 | 基本的になし |
| 柔軟性 | 法律で枠組みが決まっており制約あり | 契約で自由に設計できる |
| 費用 | 申立費用+後見人報酬 | 契約費用(公証役場・専門家報酬) |
| 向いているケース | 詐欺防止、法的に強い保護が必要な場合 | 資産運用や相続を見据えた柔軟な管理 |
5.どちらを選ぶべきか
実際の選択は「家族の状況」「本人の財産規模」「介護の見通し」によって異なります。
- 成年後見制度が向いているケース
- 高齢者が一人暮らしで家族のサポートが乏しい
- 悪質商法や詐欺に巻き込まれるリスクが高い
- 本人の財産をしっかり守りたい
- 家族信託が向いているケース
- 信頼できる家族が近くにいる
- 資産運用や相続対策も同時に考えたい
- 柔軟に財産を使えるようにしたい
実際には「任意後見契約+家族信託」を組み合わせて準備するケースも増えています。
6.利用の流れ
(1) 成年後見制度
- 家庭裁判所へ申立て(本人・配偶者・親族などが可能)
- 医師の診断書提出
- 家庭裁判所が審理し後見人を選任
- 後見人が財産管理を開始
申立てから開始まではおおむね2〜3か月かかります。
(2) 家族信託
- 家族間で話し合い、信託契約の内容を決める
- 公証役場で信託契約を公正証書にする
- 財産の名義を受託者へ移転し、管理を開始
こちらは1〜2か月程度で始められることが多いですが、専門家への依頼が推奨されます。
7.介護現場から見た制度の実際

介護施設で働いていると、認知症の方のお金のトラブルは少なくありません。
- サービス利用料が支払われず滞納になる
- 本人が詐欺に遭い、生活費がなくなる
- 家族間で「誰が管理するか」で揉める
成年後見制度を利用している方は、支払いが安定し、施設としても安心してケアを続けられることが多いです。一方、家族信託を活用しているケースでは、必要なときにスムーズに資金を引き出して介護サービスやリフォームに使うことができ、柔軟さが大きな利点になっています。
8.まとめ:早めの準備が安心につながる
認知症の介護において「お金と財産の管理」は避けて通れない課題です。
- 成年後見制度は法律で守られる強固な仕組み
- 家族信託は柔軟性が高く、生活や相続の設計に役立つ
大切なのは、本人の意思を尊重しながら、早めに準備を始めることです。判断力が残っているうちに家族で話し合い、専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士など)に相談することが安心につながります。
「介護は突然始まる」とよく言われますが、金銭面の備えがあるかどうかで家族の負担は大きく変わります。認知症と向き合うご家族には、ぜひ制度の活用を前向きに考えていただきたいと思います。
参考文献・出典
- 法務省「成年後見制度」https://www.moj.go.jp/
- 厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」
- 日本司法書士会連合会「家族信託の活用について」
- 全国社会福祉協議会「高齢者の権利擁護」



コメント