はじめに
「母がアルツハイマー型認知症と診断されたとき、頭が真っ白になりました。
一人暮らしを続けている母の家に行くと、冷蔵庫には大量の納豆。食べた形跡はなく、部屋は散らかり放題。夜中に『財布が盗まれた』と警察に何度も電話をかける姿に、どう接すればいいのか分からなくなりました。薬は残っていて、飲んでいるのかも不明。昼間はウトウトしていて、会話も減ってきています。
――これからどうすればいいのか? 介護をする家族として、何を優先したらいいのか?」
同じような戸惑いを抱えている介護家族は少なくありません。この記事では、**「介護家族が心をすり減らさずに、一歩ずつ前に進むための5つのステップ」**を紹介します。
ステップ1:まずは生活を把握し、接し方を見直す

アルツハイマー型認知症の介護で最初に大切なのは、正しい理解と生活把握です。
① 認知症を理解する
「物忘れ=すぐに叱る」「間違いを訂正する」という対応は逆効果になることがあります。本人の言動を頭ごなしに否定したり、禁止ばかりしたりすると、不安や混乱が強まり、行動・心理症状(BPSD)が悪化してしまうからです。
② NG行動を減らす
- 「違うでしょ!」と否定するのではなく、「そうなんだね」と受け止める
- 「ダメ!」と禁止するより、安全な環境を整える
- 本人の世界を理解する視点を持つ
否定や禁止は、本人の不安や混乱を強め、関係性を悪化させます。
代わりに、「一緒に探してみよう」「冷蔵庫を整理しておこうか」と寄り添う言葉がけを意識しましょう。
③ 生活環境を把握する
まずは 本人の生活実態を知ること。可能なら記録を取りましょう。
- 食事:何時ごろ、何を食べているか
- トイレ:回数や失敗の有無
- 入浴や清拭の有無
- 日中の過ごし方(テレビ、昼寝など)
- 気になる発言や行為(徘徊、不安、被害妄想など)
- 耳の聞こえ(テレビ音量などで推測できる)
- 薬の服用の様子(残薬の有無、飲み忘れ)
- 夜間の様子(徘徊や不眠など)
この「生活の見える化」は、後の医療や介護サービスにつなげるための基盤になります。
ステップ2:医療的な整理と服薬管理
生活の把握と同時に必要なのが、医療面の整理です。
① かかりつけ医との連携
認知症の診断や治療はもちろんですが、持病の管理(高血圧など)も重要です。
残薬が多い場合は、薬局や医師に相談し、服薬状況を調整してもらいましょう。
② 薬の管理を家族が補助する
- 服薬カレンダーやお薬ボックスを活用
- 服薬支援サービス(訪問薬剤師による管理)を導入
- 医師に処方の見直しを依頼
③ 医療と介護をつなぐ準備
記録してきた生活情報を、医師に伝えることが大切です。
「昼夜逆転している」「夜間徘徊が増えている」「納豆ばかり買い込んで食べない」といった具体例は、診察時に有効な情報となります。
ステップ3:介護保険サービスを導入する
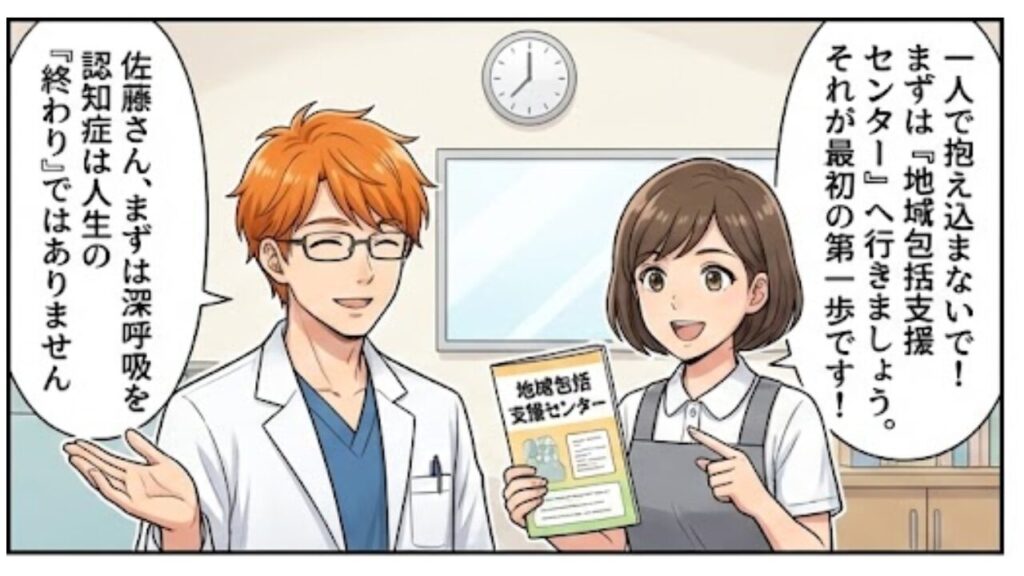
生活と医療の整理が進んだら、介護保険サービスの利用を検討しましょう。
① まずは地域包括支援センターへ
ここが介護の「入り口」です。ケアマネジャーの紹介や、サービス利用の手続きができます。ステップ1での生活記録があると、より的確なアセスメントにつながります。どのような介護を進めていくか、司令塔であるケアマネージャーとの信頼関係は特に重要です。介護認定を受けると次の②のサービスを利用できます。
② 利用できる主なサービス
- デイサービス:日中を安心して過ごせる場所。家族の休息にも。
- 訪問介護:食事・掃除・買い物の支援。
- 訪問看護:体調観察、服薬管理、医療処置。
- ショートステイ:介護者の休養や急用時に便利。
- 介護施設の入所:特別養護老人ホームやグループホームなど、認知症の状況と家族の介護状況によっては検討も必要。昼夜逆転や排泄失敗が多い場合、検討の目安となる。
③ 家族の負担を減らす目的で利用する
「本人のためだけでなく、家族が倒れないために使う」ことを意識してください。
介護保険サービスを利用するときにやってしまいがちなNGは、
- 「まだ大丈夫だから」と申請を先延ばしにする
- 「サービスを使うのは申し訳ない」と遠慮する
- 家族が全部背負い込んでしまう
認知症は進行性の病気です。早めにサービスを導入することで、本人の自立を長く保てることも多いです。
ステップ4:財産管理と金銭面の備え
生活や医療・介護がある程度形になったら、次に考えたいのが財産管理です。大事なのは、財産管理を単なる「お金の話」として切り離さないことです。
食事・薬・安全・介護サービスの利用と密接に関わるため、生活の実態を把握したうえで「どの部分に費用がかかっているのか」「無駄がないか」を見直す必要があります。
① 認知症とお金のリスク
- 同じものを繰り返し買う(納豆の買い込み)
- 財布や通帳をなくす、盗まれたと思い込む
- 詐欺被害のリスク
- 公共料金や家賃の滞納
② 初期の工夫
- 財布の中身を定額にする
- 公共料金は口座引き落としにする
- 通帳やカードは家族が保管
- 買い物は同伴か宅配利用
③ 制度を活用する
金銭面の備えは、制度を利用することで家族の負担を減らせます。
- 任意代理契約
本人がまだ判断できるうちに、家族にお金の管理を委ねる契約。 - 成年後見制度
判断能力が低下してから利用できる制度。家庭裁判所が後見人を選び、財産管理や契約を代行。 - 家族信託
財産を信頼できる家族に託し、本人や家族の生活のために使えるようにする仕組み。
これらは一度にすべて準備する必要はありませんが、介護が長期化することを考えると、どこかのタイミングで専門家(司法書士・弁護士・地域包括支援センター)に相談しておくと安心です。
ステップ5:介護者自身のケアと支え
認知症の介護では、本人の安全や生活支援に意識が集中しがちです。
しかし、忘れてはならないのが「介護する側=家族の健康や生活」です。
「父の夜間徘徊に付き合っていたら眠れなくなった」
「財布を盗られたと警察に連絡するのを止めるのに疲れ果てた」
「介護のために自分の仕事や趣味を諦めている」
こうした声は、どの介護現場でも頻繁に耳にします。
ステップ1~4で生活・医療・サービス・金銭面がある程度整ってきたら、次に必ず考えてほしいのが 介護者自身の支え です。
① 介護者の心身の疲労を放置しない
介護者は、知らず知らずのうちに心身がすり減っていきます。
- 睡眠不足(夜間対応や不安のため眠れない)
- 孤独感(「誰にも分かってもらえない」という思い)
- 体調不良(腰痛・高血圧・うつ症状など)
- 経済的負担(仕事を減らす、退職するなど)
こうした負担を軽視すると、介護うつ や 共倒れ に直結してしまいます。
介護者自身の健康は「本人の介護を続ける力」と同義です。
② 介護サービスを「家族のため」にも使う
介護保険サービスは本人のためだけではなく、家族の負担を減らすための制度でもあります。
- デイサービス:本人の活動支援+介護者の休息時間
- ショートステイ:家族が旅行・通院・休養するときに利用できる
- 訪問介護(ヘルパー):掃除・調理・買い物代行などを任せることで家族の余力が残る
「自分が頑張らないと」と抱え込むのではなく、制度を“介護者のため”にも積極的に使う視点を持つことが大切です。
③ 地域や仲間とつながる

介護は孤独になりやすいものです。
だからこそ、「地域で支え合う仕組み」を活用しましょう。
- 認知症カフェ:同じ立場の人と悩みを共有できる場所
- 家族会:経験者同士で具体的な工夫や制度活用法を学べる
- 地域包括支援センター:介護者の悩みにも相談に乗ってくれる
- オンラインコミュニティ:時間や距離に縛られず気軽に交流できる
「自分だけじゃない」と思えることが、介護を長く続けるための支えになります。
④ 「介護の手を離すこと」は「投げ出すこと」ではない
介護者が一番抱きやすい葛藤が、「休んだら悪いのではないか」「親を放っておけない」という罪悪感です。
しかし、介護サービスを利用したり、誰かに頼ったりすることは、決して親を見捨てることではありません。
むしろ、介護者が心身ともに余裕を保つことこそ、本人の安心につながります。
「少し距離をとる」「休む」ことは、介護を継続するための大事な戦略なのです。
⑤ 介護者の生活も大切にする
介護は長期戦です。
その間、介護者自身の人生も進んでいきます。
- 趣味や友人との時間を持つ
- 健康診断や通院を怠らない
- 就労を続ける方法を検討する(介護休業制度の活用など)
- 家族内で役割分担をする
読者へのメッセージ

介護は、誰にとっても初めての経験です。
そして、多くの人が「自分だけが苦しんでいる」と思い込んでしまいます。
でも、本当は違います。
あなたのように悩み、迷い、試行錯誤している家族は全国にたくさんいます。
アルツハイマー型認知症と診断されたとき、確かに不安は大きいでしょう。
けれども、**「生活を把握し、医療とつなぎ、介護保険を活用し、財産を守り、家族自身を支える」**という5つのステップを踏めば、少しずつ前に進めます。
介護は長い道のりですが、あなたは一人ではありません。
地域包括支援センターや医師、ケアマネジャー、そして同じ立場の家族が、きっと支えになってくれます。
どうか心が折れそうになったときには、「今はステップ1をやるときだ」「今日はステップ3に相談してみよう」と、小さな一歩に分けて考えてください。
介護はマラソンのようなものです。ペースを守り、休みながら、仲間と一緒に走り続けることが大切です。
そして、あなた自身の笑顔こそが、本人にとって最大の安心につながります。
参考文献・出典
- 厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」
- 厚生労働省:介護保険制度の概要
- 日本認知症学会:認知症疾患治療ガイドライン
- 地域包括支援センター業務マニュアル
「『薬飲んだっけ?』『また飲んでない!』…そんな毎日のやり取りに疲れていませんか?
認知症介護において、お薬の管理は大きな火種になりがちです。飲み忘れや飲みすぎ(過量服用)は、体調悪化だけでなく、家族のイライラを増幅させます。
一目でわかる『お薬カレンダー』や『セットボックス』を使うだけで、確認のストレスは激減します。薬のプロとして断言します。管理の仕組み化は、早期に取り組むべき最重要課題の一つです。」👇
「どうして、何度言ってもわからないの?」「なぜ、わざと困らせるようなことをするの?」
介護中、そんな怒りと悲しみに震えることはありませんか?でも実は、ご本人にはご本人の『正当な理由』があるのです。
この本は、認知症の方が生きている『世界』を、まるで旅行ガイドのように案内してくれます。「お風呂を嫌がるのは、お湯が真っ黒な穴に見えているからかもしれない」——そんな『理由』を知るだけで、不思議と怒りは消え、優しさが戻ってきます。
介護のテクニックを学ぶ前に、まずは『相手の住む世界』を知ってみませんか?読むだけで、あなたの肩の荷がスッと降りる一冊です。👇
「さっきご飯を食べたばかりなのに、まだ食べていないと言う」 「財布を盗まれたと、いつも私のせいにする」
親のそんな行動に、「いい加減にして!」と叫び出したくなることはありませんか?でも、もしその行動すべてに**『明確な法則』**があるとしたらどうでしょう。
この本は、数多くの認知症患者を診てきた専門医・杉山孝博先生が導き出した**「認知症の9大法則・1原則」**を解説した一冊です。
認知症の症状は、決してデタラメではありません。法則を知れば、「ああ、今は『記憶障害の法則』が働いているんだな」と、一歩引いて冷静に対処できるようになります。
「相手を変えることはできないが、こちらの対応は変えられる」。その具体的なテクニックが詰まった、まさに介護の教科書。文庫本サイズで持ち運びやすく、心が折れそうな時のお守り代わりになる一冊です👇






コメント