高齢者や認知症の方の介護において、「薬を飲みたがらない」「薬を口に入れても吐き出してしまう」といった“薬の拒否”はよく見られる課題のひとつです。服薬は病気の治療や症状の安定に直結するため、介助する側としては強い不安や焦りを感じやすいものです。しかし、無理やり飲ませようとすると誤嚥や不信感につながり、かえって服薬が難しくなる場合もあります。
この記事では、薬の拒否があるときに介護者や家族がとれる安全で実践的な服薬介助方法についてまとめます。
1. なぜ薬を拒否するのか ― 背景を理解する

薬を拒否する行動には、必ず理由があります。その理由を探ることが服薬支援の第一歩です。
よくある原因
- 認知症による理解力の低下
「飲み込むものだ」という認識がなくなっている、「これは毒ではないか」と疑う、「さっき飲んだ」と思い込むなど。 - 薬の形や味、においへの不快感
大きすぎる錠剤、苦味、独特の匂いが嫌悪感を誘う。 - 身体的な問題
嚥下機能の低下により飲み込みづらい。口内炎や歯の不調で痛みがある。 - 心理的な要因
気分の落ち込みや介助者への不信感。服薬に対する抵抗感。
拒否の背景を観察・記録することで、対応の方向性が見えてきます。
2. 基本の姿勢 ― 無理強いせず「安心感」を優先
服薬拒否の場面で最も重要なのは、無理やり飲ませないことです。無理強いは誤嚥のリスクを高めるだけでなく、介助者への不信感を強め、次回以降さらに拒否が強くなることがあります。
ポイント
- 介助者は落ち着いた声かけをする
- 「一緒に確認して安心できる環境」をつくる
- 時間をずらして再挑戦する柔軟さを持つ
3. 安全な服薬介助の工夫
(1) 声かけと説明の工夫
- 「お薬の時間ですよ」ではなく、「血圧を整える大切なお薬ですよ」と効果を伝える。
- 「あとで飲みましょう」と選択の余地を与えることで安心感を高める。
(2) 環境を整える
- テレビや騒音を避け、落ち着ける場所で行う。
- 水やお茶を先に口に含んでもらい、飲み込みやすい状態にする。
(3) 薬の形状や剤形の工夫
薬剤師と相談することで、以下の工夫が可能です。
- 錠剤を小型のものや口腔内崩壊錠に変更
- 粉薬に変更し、とろみ飲料やゼリーに混ぜる
- シロップ剤に変更する
※ただし、薬によっては粉砕や混合が禁忌の場合もあるため、必ず医師・薬剤師に相談してください。
(4) 食べ物・飲み物と一緒に
- ヨーグルトやプリンなど、飲み込みやすい食品に包む
- 苦味が強い薬はジュースやゼリーと一緒に摂取する
ただし、グレープフルーツジュースなど一部の飲料は薬の効果に影響するため避ける必要があります。
4. 認知症の方への対応ポイント
認知症の方は薬を「知らないもの」「危険なもの」と感じやすいため、心理的安心感が何より大切です。
有効な方法
- 見せ方を工夫する
薬をまとめて見せるのではなく、一錠ずつ提示する。 - 役割意識を活かす
「お薬を飲むと、今日も畑に出られますよ」など、その人にとって意味のある行動と関連づける。 - 肯定的な言葉を使う
「飲まないとダメ」ではなく「飲むと安心できますよ」と前向きに。
5. 薬剤師・医師との連携
薬の拒否が続く場合は、介護者だけで抱え込まず、医師や薬剤師に相談しましょう。
専門職ができること
- 不要な薬がないかをチェック(ポリファーマシー対策)
- 副作用や飲み合わせの確認
- 剤形変更の提案(貼付剤や液剤への切り替えなど)
医師・薬剤師との情報共有は、安全な服薬支援の基盤です。
6. 誤嚥を防ぐために注意すべきこと
薬を無理に口に入れると誤嚥性肺炎のリスクがあります。安全な服薬介助のために、以下の点を必ず守りましょう。
- 座位を基本とする(背もたれを60度以上起こす)
- 一度に多くを口に入れない
- 水分補給を促す
- 服薬後も数分間は座位を保つ
7. 家族や介護スタッフが心がけたいこと

- 「飲めなかった日があっても仕方ない」と柔軟に考える
- 服薬の可否を日誌に記録し、次の医師受診時に報告する
- 家族と介護スタッフで共通認識を持ち、対応を統一する
まとめ
薬の拒否は高齢者や認知症の方にとって珍しいことではありません。大切なのは、無理強いせず、安心できる環境と方法を整えることです。声かけや環境調整、薬の形状変更といった工夫を取り入れながら、安全に服薬できるよう支援していきましょう。そして、拒否が続くときは早めに医師や薬剤師と連携することが、安全な介護の第一歩です。
出典
- 厚生労働省:「高齢者の医薬品適正使用の指針」第1版(2018年)
- 日本老年医学会:「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 2023」
- 国立長寿医療研究センター:「認知症の人の服薬支援に関する研究」


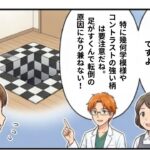
コメント