はじめに
認知症の方にとって生活環境は、安心感や行動の安定に大きな影響を与えます。中でも「音・光・色」といった五感に関わる要素は、脳や感情に直接働きかけるため、ケアの質を高める有効な手段です。
たとえば音楽を聴いて気持ちが穏やかになったり、適切な光で夜の不安が和らいだり、色の工夫で食欲や行動が改善したりすることがあります。本記事では、介護現場や家庭で実践されている「音・光・色」を活用した認知症ケアの実例を紹介し、取り入れる際の注意点についても解説します。
音を活用した認知症ケア
音楽療法(ミュージックセラピー)
音楽は感情や記憶に深く結びついており、認知症ケアでよく用いられます。
- 実例
・昭和歌謡を流したところ、普段は会話の少ない利用者が歌詞を口ずさみ、自然に会話が生まれた。
・家族と一緒に昔の歌を歌うことで、笑顔が増え、交流の時間が豊かになった。 - 効果
長期記憶に残りやすい音楽は「自分らしさ」を呼び戻すきっかけになります。リズムに合わせて体を動かすことは運動機能の維持にも役立ちます。
環境音による安心感
静かすぎる環境は不安を招くことがあります。生活音や自然音は「人の気配」を感じさせ、安心感を与えます。
- 実例
・食事中に川のせせらぎを流すと、落ち着いて食事ができた。
・夜間、廊下に小さな環境音を流すと「誰かが近くにいる」という感覚が生まれ、不安が和らいだ。
声かけの工夫
声そのものも「音のケア」です。高圧的なトーンではなく、落ち着いた声かけが大切です。
- 実例
・「トイレに行きましょう」よりも「一緒に少し歩いてみませんか?」と声をかけた方がスムーズだった。
・名前をやさしく呼びかけることで、拒否的な行動が減った。
耳の聞こえ・補聴器の活用
認知症の方の中には、加齢による聴力低下を抱えている方も多くいます。聞き取りづらさは「わからない」「不安」という気持ちを強め、結果的に混乱や拒否的行動につながります。
- 実例
・補聴器を調整し直したところ、声かけへの反応が良くなり、ケアがスムーズになった。
・集団でのレクリエーションでも音が届くよう、スピーカーを活用したら参加意欲が高まった。 - ポイント
補聴器の使用や定期的な耳のケアは、音を活かす取り組みの前提となります。「聞こえやすさ」を整えることが安心感の第一歩です。
光を活用した認知症ケア
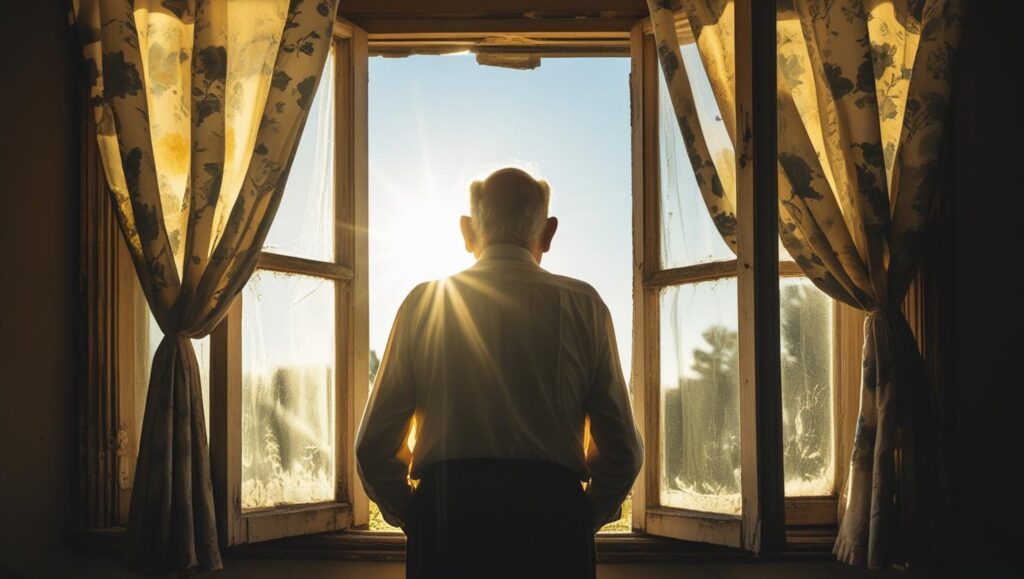
光と体内リズム(サーカディアンリズム)
認知症では昼夜逆転や不眠が起こりやすく、光による調整が有効です。
- 実例
・午前中の日光浴で夜間の入眠がスムーズになった。
・朝は白色光、夕方は暖色系に切り替える照明を導入し、夕暮れ時の不安(サンセット症候群)が減少した。
夜間照明と転倒予防
暗さは転倒リスクを高めます。足元灯や間接照明で安全性を確保することが大切です。
- 実例
・廊下にフットライトを設置し、夜間トイレへの移動が安心して行えるようになった。
・ベッドサイドランプを設置し、不意に起きた際の不安が軽減された。
季節感の演出
光を工夫することで季節感を補い、時間や季節感覚を保つ助けになります。
- 実例
・行事に合わせてイルミネーションを取り入れると、会話や回想が生まれた。
・梅雨の時期に明るい照明を活用し、気分の落ち込みが和らいだ。
色を活用した認知症ケア

色彩と感情への影響
色は感情に大きく作用します。暖色は活力を促し、寒色は落ち着きをもたらします。
- 実例
・赤やオレンジの食器で食欲が増えた。
・青や緑のカーテンで落ち着きが生まれ、徘徊が減った。
空間認識のサポート
色のコントラストを活かすと、場所や物の認識が容易になります。
- 実例
・トイレのドアを黄色に塗ると、場所がわかりやすくなった。
・階段に黄色いラインをつけると、転倒が減った。
模様や錯視への注意
認知症の方は視覚認知が低下し、模様が錯覚を生むことがあります。
- 実例
・模様のあるお皿を「虫がいる」と誤解し、食事を拒否した利用者が、無地のお皿に替えると安心して食べるようになった。
・床の模様を「段差」や「水たまり」と誤認し、歩行をためらうケースがあったため、シンプルなデザインに変更した。 - ポイント
色だけでなく模様や柄の有無にも配慮し、錯視を避ける工夫が重要です。
個人の好みに合わせた色づかい
本人の好きな色や思い出の色を取り入れると、安心感につながります。
- 実例
・本人が好んでいたピンク色を居室に取り入れると、表情が穏やかになった。
・思い出の品と合わせた色づかいで「自分の部屋」という認識が深まった。
実際に取り入れる際のポイント
- 過剰な刺激を避ける
音や光、色は強すぎると逆効果になることがあります。心地よい範囲を見極めましょう。 - 本人の反応を観察する
一人ひとりに合う方法は異なります。試しながら反応を観察することが大切です。 - 医療・介護スタッフとの連携
薬の副作用や体調で感覚の受け取り方は変わります。医師や薬剤師と共有しながら取り入れると安心です。
まとめ

音・光・色は認知症ケアにおいて「生活を支えるツール」として有効です。
- 音楽や環境音、補聴器の調整によって安心感や交流が生まれる
- 光で体内リズムを整え、不安や転倒を防ぐ
- 色彩や模様の工夫で感情や空間認識を支え、錯視を避ける
こうした取り組みは、特別な設備がなくても家庭や施設で工夫できます。小さな配慮が、認知症の方の「その人らしさ」を引き出すケアにつながります。
出典
- 厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」
- 日本音楽療法学会「音楽療法の効果について」
- 照明学会「高齢者施設における照明のあり方」
- 日本色彩学会「色彩と心理・行動の関係」
- 日本老年医学会雑誌「高齢者の感覚機能と認知症」



コメント