高齢者にとって「転倒」「転落(車いすから落ちる)」は、生活の質を大きく左右するリスクです。特に認知症のある方は、転倒による骨折や入院をきっかけに、認知機能や身体機能がさらに低下しやすい傾向があります。介護現場や家庭で「どうすれば転倒を防げるか」は重要な課題ですが、単なる環境整備だけでは十分とはいえません。
薬の副作用や生活習慣、認知症特有の行動特性を総合的に理解し、日常の中で小さな工夫を積み重ねることが大切です。
本記事では、薬と生活習慣の両面から考える転倒予防と認知症ケアについて、介護者や家族が現場で役立てられる視点を整理します。
1.高齢者と転倒リスク

高齢者は加齢に伴い筋力やバランス機能が低下し、視力・聴力・反射神経も衰えます。認知症のある方では、さらに次のようなリスクが加わります。
- 空間認知の低下で段差や障害物に気づきにくい
- 注意力や判断力の低下で反応が遅れる
- 徘徊や焦燥から突然動き出す
- 薬の副作用やせん妄による混乱
つまり、身体機能の低下+認知機能の低下+薬の影響が重なり、転倒の危険性が高まるのです。
2.薬による転倒リスクと注意点
薬は高齢者の健康維持に欠かせませんが、副作用が転倒につながることがあります。特に認知症ケアでは、以下のような薬剤に注意が必要です。
(1) 睡眠薬・抗不安薬
- ふらつき、日中の眠気、注意力低下を招きやすい
- 長時間作用型は翌日まで影響が残る
(2) 抗うつ薬・抗精神病薬
- 鎮静作用で歩行が不安定になる
- パーキンソン症状(すくみ足、手の震え)を助長することがある
(3) 血糖降下薬
- 低血糖によるふらつきや意識消失から転倒につながる
- 食事摂取量が安定しない高齢者では特に注意が必要
(4) 降圧薬・利尿薬
- 起立性低血圧により立ちくらみを起こす
- 利尿薬は夜間のトイレ移動を増やし、転倒リスクを高める
(5) 下剤
- 夜間や早朝の急な排泄欲求により慌てて移動し、転倒を招くことがある
(6) 抗てんかん薬・オピオイド鎮痛薬
- 眠気、ふらつき、集中力低下が起こりやすい
薬の影響は人によって異なるため、新しい薬が処方された時や用量が変わった時には、せん妄やふらつきが出ていないか観察することが重要です。
定期的に医師や薬剤師に相談し、必要に応じて減薬や変更を検討しましょう。
3.生活習慣・環境からの転倒予防
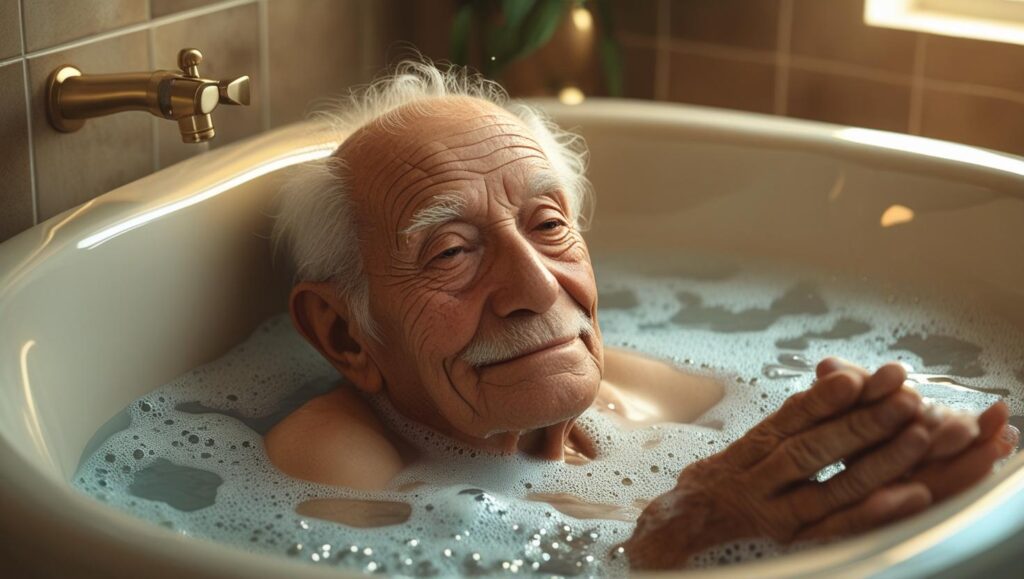
薬の調整に加えて、生活や環境を整えることで転倒リスクを大きく減らせます。
(1) 運動習慣
- 椅子からの立ち座り、かかと上げ運動で下肢筋力を維持
- 理学療法士指導によるバランス訓練
(2) 栄養管理
- 筋肉維持のためにたんぱく質をしっかり摂取
- 骨粗鬆症予防にカルシウム・ビタミンDを意識
(3) 住環境の整備
- 段差解消、手すり設置、滑り止めマットを使用
- 廊下やトイレの照明を明るく
- ベッドサイドに転倒衝撃を和らげるマットを敷く
(4) トイレ・排泄動作の工夫
- 利尿剤や下剤で排泄回数が増える人には、夜間の移動を最小限にする工夫を
- ベッド近くにポータブルトイレを置く
- トイレ内にも手すりを設置
(5) 入浴時の安全
- 入浴は転倒が多い場面の一つ
- 浴槽の出入りに手すりを設置
- 浴室マットを滑りにくい素材にする
- 見守りを行う
(6) 車いす利用時
- 車いすからの転落事故は少なくない
- フットレストやブレーキの確認を徹底
- 移乗の際には必ず声をかけ、介助を行う
4.認知症ケアにおける転倒予防の視点
認知症の方には、一般的な転倒予防策に加えて特有の工夫が必要です。
- 声かけと安心感:急に手を引かず、落ち着いてアイコンタクトをとる
- 本人のペース尊重:せかさず、本人の動作を待つ
- 行動パターンの把握:徘徊やトイレ頻回など、リスクが高い時間帯を見守る
- せん妄への注意:薬の変更後や感染症罹患時に混乱が起こりやすく、転倒リスクが増す
- ケアチームで情報共有:介護職・看護師・医師・薬剤師で「最近ふらつきが増えた」などの情報を共有
5.家族ができるサポート

家庭でケアを担う家族も、転倒予防の重要なパートナーです。
- 薬の残数や服薬状況をチェックし、重複服薬を防ぐ
- 家の中の環境を定期的に点検する
- 転倒後は「なぜ起きたか」を振り返り、再発防止につなげる
- 本人の自立を尊重しつつ、危険な場面は見守りで補う
まとめ
転倒は高齢者、とりわけ認知症の方にとって重大なリスクです。
薬の副作用やせん妄、排泄や入浴など日常の動作、車いすからの転落など多岐にわたる要因を理解し、生活環境を整えることが不可欠です。
- 薬は定期的に見直し、低血糖や起立性低血圧などに注意
- 排泄・入浴・移動など「転倒しやすい場面」に具体的な対策を
- ベッドサイドマットや手すりなどの環境整備で被害を最小限に
- 認知症特有の行動やせん妄を理解し、声かけや見守りを工夫する
介護者や家族の小さな工夫の積み重ねが、本人の安心と生活の質の向上につながります。
出典
- 厚生労働省「高齢者の転倒・骨折予防マニュアル」
- 日本老年医学会「高齢者医療ガイドライン」
- 日本薬剤師会「高齢者と薬物療法」
- 認知症介護研究・研修東京センター資料



コメント