はじめに
私は薬剤師として地域活動の一環で「認知症カフェ」に参加することがあります。そこでは、参加者からよくこんな質問を受けます。
「認知症になりにくい生活習慣ってあるんですか?」
「認知症を予防するには、どんな食事をすればいいのでしょうか?」
こうした質問は、それだけ多くの方が認知症予防に関心を持っていることの表れです。今回は、日常生活の中で実践できる生活習慣と、認知症予防に期待される食事について、科学的根拠を交えながら詳しく解説します。
1. 認知症予防につながる生活習慣

1-1. 適度な運動と身体活動
運動や身体活動は、認知症予防の中でも非常に重要な要素です。理由の一つは 筋力低下によるフレイル(虚弱)の防止 です。
フレイルが進行すると転倒や骨折のリスクが高まり、活動量の低下や社会的な孤立につながります。その結果、認知症の発症リスクも高まることが分かっています。
具体的な取り組み例
- 有酸素運動:ウォーキングやジョギング、サイクリングなどを週3〜5回、30分程度行う
- 筋力トレーニング:スクワットや軽いダンベル運動、チューブトレーニングで下肢筋力を維持
- 日常生活の中の活動量確保:エレベーターではなく階段を使う、買い物や掃除を積極的に行う
これらの活動は、脳の血流を改善し、脳細胞の活性化を促すと報告されています。
1-2. 社会的交流と心の刺激
人とのつながりは、脳に大きな刺激を与えます。社会的交流を続けることで、脳の認知機能が活性化し、孤独やうつ状態の防止にもつながります。
その理由は
- 人との会話は、言語機能や記憶力の維持に役立つ
- コミュニティ参加は「居場所」をつくり、孤立を防ぐ
- 趣味やボランティア活動は新しい刺激となり、脳の可塑性を高める
具体的な取り組み例
- 地域のサークルや趣味の会に参加する
- 認知症カフェやボランティア活動で他者と交流する
- 家族や友人と積極的に会話を楽しむ
1-3. 睡眠の質の向上
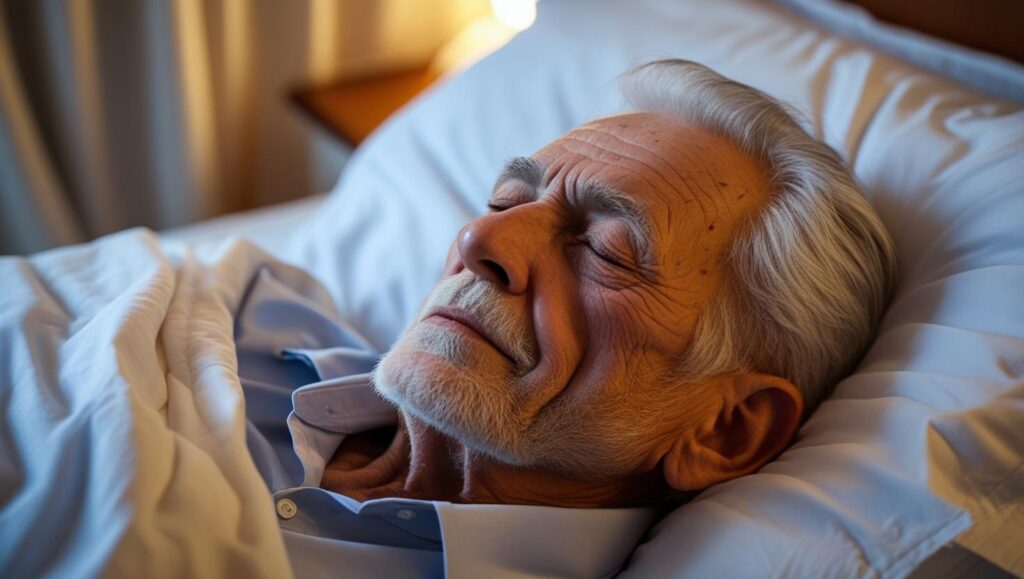
睡眠は脳を休め、記憶を整理するために不可欠です。質の高い睡眠を取ることで、アミロイドβが除去されて、認知症予防につながります。特に 昼夜逆転の防止 は重要です。昼夜逆転は生活リズムを乱し、認知機能を低下させる要因となるからです。
質の良い睡眠を確保するポイント
- 朝の光を浴びて体内時計をリセット
- 昼間はできるだけ身体を動かす
- 就寝前はスマホやテレビのブルーライトを避ける
- 昼寝は30分以内にとどめる
1-4. ストレス管理と気分の健康
なぜなら、ストレスは脳に悪影響を与えるだけでなく、うつ症状を引き起こし、認知症のリスクを高めます。さらに、うつ状態になると日中の活動量が低下し、結果的に昼夜逆転やBPSD(行動・心理症状)の発症リスクが高まります。
ストレス対策の具体例
- 深呼吸やヨガ、瞑想などのリラクゼーション法
- 趣味に没頭する時間を持つ
- 日記を書いて気持ちを整理する
- 定期的に誰かに話を聞いてもらう
気分の健康を保ち、活動的な日常を送ることが、認知症予防に大きな役割を果たします。
2. 認知症予防に期待される食事

食事は、認知症予防の大きな柱です。特に「地中海食」や「MIND食(マインド食)」が注目されています。これらの食事法は、脳の健康を保つための栄養素をバランス良く摂取できる点が特徴です。
2-1. 抗酸化作用のある食品
野菜、果物、ナッツ類には抗酸化物質が豊富に含まれています。これらは脳細胞を酸化ストレスから守り、老化を防ぐ働きがあります。
具体例
- 緑黄色野菜(ほうれん草、ブロッコリー)
- 果物(ブルーベリー、いちご)
- ナッツ(アーモンド、くるみ)
2-2. 良質な脂質の摂取
青魚に含まれるオメガ3脂肪酸(EPA・DHA)は、脳の神経細胞を保護し、炎症を抑える効果があります。
具体例
- サバ、イワシ、サンマなどの青魚を週2〜3回食べる
- オリーブオイルを料理に活用する
2-3. 糖質・塩分の摂り過ぎに注意
糖質や塩分の過剰摂取は、動脈硬化や高血圧を引き起こし、脳血管性認知症のリスクを高めます。加工食品を控え、できるだけ自然な食材を選ぶことが重要です。
2-4. 食習慣の工夫
- 朝食をしっかり摂ることで生活リズムを整える
- 食事を家族や友人と一緒に楽しむことで、社会的刺激を得られる
- 食べ過ぎや飲み過ぎを防ぎ、体重を適正に維持する
まとめ
認知症予防は特別なことではなく、 日常生活の小さな積み重ね で取り組めるものです。
- 適度な運動でフレイルを防ぐ
- 社会的交流で脳を刺激する
- 良質な睡眠で脳を休める
- ストレスを溜めず、気分を安定させる
- 栄養バランスの取れた食事を続ける
このような習慣を意識的に取り入れることで、脳と心の健康を長く維持することができます。



コメント