「認知症=アルツハイマー型」と思われがちですが、実際には原因や症状の異なる複数のタイプがあります。それぞれに適した対応や治療方法を知ることが、患者さんや家族の負担を減らす第一歩です。ここでは、代表的な認知症の種類・割合・特徴・対応方法をまとめた表と、その詳細を解説します。
認知症の種類と概要(割合・特徴・診断・薬物治療)
| 認知症名 | 割合 | 主な特徴 | 診断のポイント | 薬物治療の要点 |
|---|---|---|---|---|
| アルツハイマー型 | 67.6% | 顕著な中核症状、BPSD | MRI、認知検査 | アセチルコリン阻害薬、NMDA拮抗薬、少量非定型抗精神病薬、抗うつ薬、漢方 |
| 血管性 | 19.5% | 梗塞・出血による段階的悪化 | CT/MRI、脳血管病変 | 生活習慣病管理/BPSD時は糖尿病合併例に非定型抗精神病薬投与注意 |
| レビー小体型 | 4.3% | 幻視、パーキンソン症状、筋力低下・嚥下障害・転倒、睡眠障害 | DSM-5基準+SPECT/MIBG | ドネペジル、少量レボドパ、抑肝散、抗精神病薬は慎重 |
| 前頭側頭型 | 1.0% | 人格・行動変化、社会性欠如、介護困難 | 脳萎縮+行動症状 | 根本治療なし、環境調整と介護者支援 |
| その他 | 約7.6% | 正常圧水頭症(脳室拡大、歩行障害、尿失禁) クロイツフェルト・ヤコブ病(急速進行性) アルコール性認知症 外傷後認知症 | 原因により異なる | 原因疾患に応じた治療 |
1. アルツハイマー型認知症

特徴・原因
- 全認知症の約2/3を占め、特に女性に多い
- 脳内のアミロイドβやタウ蛋白が異常蓄積し、海馬から脳全体に神経細胞の障害が進行
- 初期は新しいことを覚えられない「記銘障害」が目立ち、徐々に見当識障害や判断力低下が出現
診断方法
- MRIやCTで海馬の萎縮を確認
- 認知機能検査(MMSE、長谷川式スケール)
- 血液検査で甲状腺機能やビタミン欠乏などの可逆性認知症を除外
対応方法
- 非薬物療法を積極的に導入(体操、音楽療法、回想法、動物介在療法、脳トレなど)
- 安定した生活リズムの維持、過度な刺激を避ける環境整備
- 家族や介護者への教育と支援
薬物治療
- 中核症状:
- アセチルコリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン)
- NMDA受容体拮抗薬(メマンチン)
- BPSD(行動・心理症状):
- 少量の非定型抗精神病薬(リスペリドン、クエチアピン、オランザピンなど)
- 抗うつ剤(アリピプラゾール、ブレクスピプラゾール[レキサルティは適応あり])
- 漢方薬(抑肝散、人参養栄湯など)
2. 血管性認知症
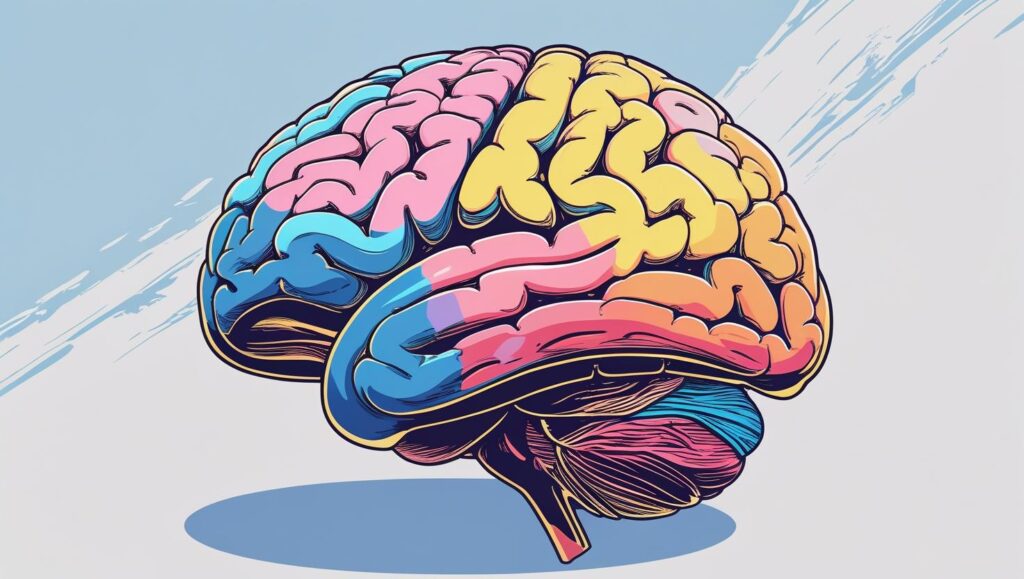
特徴・原因
- 脳梗塞や脳出血など脳血管障害によって生じる。障害される場所によって症状は様々。
- 認知機能低下が段階的に悪化するのが特徴
- 動脈硬化や生活習慣病(高血圧、糖尿病、高脂血症)との関連が深い
診断方法
- CT/MRIで脳血管病変を確認
- Hachinski虚血スコアやDSM-5基準で評価
- 血液検査で動脈硬化リスク因子を確認
対応方法
- 生活習慣の徹底管理(減塩、禁煙、適度な運動、糖尿病・高血圧のコントロール)
- 抗血小板薬や抗凝固薬で再発予防
- リハビリテーションによる機能維持
薬物治療
- 基礎疾患の薬物治療。基礎疾患の管理で進行や行動異常をある程度抑えられることもある。
- BPSD発現時は非定型抗精神病薬を用いるが、糖尿病合併例では血糖コントロール悪化に注意
3. レビー小体型認知症

特徴・原因
- 男性に多い
- α-シヌクレインが蓄積して神経細胞が障害
- 症状は「認知機能の変動」「幻視」「パーキンソン症状」が三大特徴
- その他:嚥下障害(筋力低下)による誤嚥・拒食・脱水、転倒リスクが高い
- 意欲低下、レム睡眠行動障害がみられる。
診断方法
- DSM-5基準に基づく臨床診断
- SPECTやMIBG心筋シンチで補助診断
対応方法
- 転倒防止の住環境整備
- 嚥下訓練や食事形態の工夫。拒食でフレイルに陥りやすい。食事と筋力維持も重要。
- 幻視は否定せず安心させる対応
薬物治療
- 認知機能、意欲低下:ドネペジル(適応あり)
- 運動症状:少量レボドパ(悪化の可能性に注意)
- 幻視や不安:抑肝散や少量の抗精神病薬(クエチアピンなど、慎重に)
- RBD(レム睡眠行動障害):クロナゼパムなど
4. 前頭側頭型認知症
特徴・原因
- 前頭葉や側頭葉の萎縮が原因
- 人格や行動の変化、社会性の欠如、脱抑制、常同行動などが顕著
- 介護が最も困難とされる認知症のひとつ
- 記憶は比較的保たれるが、感情や行動のコントロールが著しく障害される
診断方法
- MRI/PETでの脳萎縮確認
- 症状観察とDSM-5基準で診断
対応方法
- 環境調整(刺激を減らす、行動を予測可能にする)
- 介護者への心理的サポート
- 行動療法やスケジュール管理
薬物治療
- 特効薬なし
- 攻撃性や興奮が強い場合、少量の抗精神病薬を慎重に使用して介護介入の下地を作る
5. その他の認知症
- アルコール性認知症、混合型認知症、正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫など
- 外科的治療で改善する場合もあるため早期診断が重要
6.まとめ

それぞれの認知症には特徴的な症状があり、対応方法も異なる場合があります。早期診断によって、その他の認知症や疾患の可能性を排除し、タイプの見極めを行うことが重要です。
早期受診は診断方針を早めに決定し、進行を遅らせるだけでなく、介護の介入をスムーズにします。
非薬物療法、薬物療法、生活環境の整備、そして適切なコミュニケーションやリハビリテーションを日常生活に組み込み、患者本人が過ごしやすく、家族が介護しやすい形を目指していきましょう。



コメント