はじめに
認知症の方にとって、薬を正しく飲むことは大きな課題です。飲み忘れや重複服薬だけでなく、嚥下の問題や落薬、注意散漫による服薬ミスも少なくありません。服薬が適切に行われなければ、病気のコントロールが不十分になるだけでなく、副作用や転倒、入院につながる危険性もあります。
介護現場やご家庭でできる「服薬環境の整備」は、安全で安心な療養生活を支えるうえで欠かせません。ここでは薬剤師の視点を交えながら、具体的な工夫や対策をまとめます。
1. 服薬ミスが起こりやすい背景とその対策

1-1. 飲み忘れ
- 背景:記憶障害により「もう飲んだかわからない」「今飲む時間か忘れてしまう」ことが多い。
- 対策:
- 一包化やピルケースを活用し、飲んだかどうかが一目で分かる仕組みを整える。
- アラームやカレンダーにより「飲むタイミング」を外部刺激で補う。
1-2. 重複内服
- 背景:薬が残っていると不安になり、再度服用してしまう。
- 対策:
- 食卓など決まった場所に薬を置き、服薬後に家族や介護者が確認する。
- 飲んだ後にチェック表に印をつける習慣を取り入れる。
1-3. 取り違え
- 背景:形や色が似ている錠剤・カプセルを見分けられない。
- 対策:
- 薬剤師に依頼し一包化にする。
- 市販薬やサプリメントは別の場所に保管し、容器を色分けする。
1-4. 服薬拒否
- 背景:薬の必要性が理解できない、味やにおいが嫌で飲みたがらない。
- 対策:
- 薬剤師に相談し、口腔内崩壊錠やシロップなど飲みやすい形に変更。
- 「これは血圧を守るお薬ですよ」と短く具体的に伝える。
1-5. 嚥下困難
- 背景:錠剤やカプセルを飲み込めず、口腔内に薬が残ることがある。誤嚥のリスクもある。
- 対策:
- 薬剤師に相談し、粉砕、口腔内崩壊錠、ゼリー製剤などに変更できる場合がある。
- トロミ剤入りのゼリーと一緒に飲む。
- 服薬後に口腔内を確認し、薬が残っていないか確認する。
1-6. 落薬
- 背景:手の震えや不自由さで薬を落としたり、口に入れても出てしまうことがある。
- 対策:
- 机に薬を置き、スプーンやピンセットで本人に渡す。
- 服薬ゼリーに包んで口に運ぶと落下を防げる。
- 床に落ちても見つけやすいよう、服薬はテーブル上で行う。
1-7. 注意散漫
- 背景:テレビや会話に気を取られ、服薬に集中できない。飲んだふりをして残すこともある。
- 対策:
- 服薬の時間は環境を落ち着かせ、声かけをして集中できる場を作る。
- 食後に「一緒にお薬を飲みましょう」と家族や介護者が同席する。
- 服薬後に口腔内を確認し、実際に飲み込んだかを確かめる。
2. 環境整備の工夫

2-1. 薬の整理と見える化
- 一包化で1回分をまとめる。
- 大きめのカレンダー式ピルケースを活用。
- 飲み終えた袋やケースを捨てる・チェック表に記録する習慣を作る。
2-2. 飲む時間の工夫
- アラームやスマホ通知を利用。
- 食事と結びつけて「ごはんの後に必ず薬」という習慣をつける。
- デイサービスや施設では、スタッフが声かけを統一する。
2-3. 飲みやすさの工夫
- ゼリーや水に浮かべることで誤嚥や落薬を防ぐ。
- 錠剤が大きい場合は薬剤師に相談して変更する。
- 嚥下リハビリを並行して行うと、服薬全般の安全性が高まる。
3. 多職種での連携
服薬管理は家族や介護職だけで抱えると負担が大きいものです。
- 薬剤師:在宅訪問で薬の残数確認、一包化、飲みやすい剤形への変更をサポート。
- 医師:ポリファーマシーが疑われる場合、処方薬を見直す。
- 看護師・介護職:日々の体調変化や服薬拒否の状況を共有し、改善策を検討。
4. 実例紹介
- 例1:飲み忘れが多い方
一包化+食卓にピルケース設置+チェック表で確認。飲み忘れが大幅に減少。 - 例2:嚥下が難しい方
錠剤を口腔内崩壊錠に変更。服薬ゼリーを併用し、口腔内残留が減った。 - 例3:落薬しやすい方
介護者がスプーンで渡す方式に変更。床に薬を落とさなくなり安心して服薬できるようになった。 - 例4:注意散漫な方
テレビを消して静かな環境で服薬。介護者が「今はお薬の時間です」と声かけ。飲み残しが解消。
5. ご家族・介護者が意識すべきこと

- 本人任せにしない:認知症が進むと必ずサポートが必要になる。
- 小さな変化を記録する:ふらつき、飲み残し、拒否などをメモして医師・薬剤師に伝える。
- 工夫を積み重ねる:完璧を目指すのではなく、一つずつ改善を試みる。
まとめ
認知症の方の服薬ミスは「記憶障害」だけでなく、嚥下困難・落薬・注意散漫といった身体的・行動的な要因も大きく関わっています。
一包化やピルケース、服薬ゼリーなどの工夫、アラームやチェック表による「見える化」、そして薬剤師や医師との連携が、服薬の安全を守るカギとなります。ご家族や介護スタッフは「本人が安心して薬を飲める環境づくり」を意識しながら、負担の少ない方法を選びましょう。
大切なのは「本人が安心して薬を飲める環境をつくること」。ご家族や介護者が無理なく続けられる方法を選びながら、服薬の質を高めていきましょう。
参考文献・出典
- 厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」
- 日本薬剤師会「在宅医療における薬剤師の役割」
- 認知症介護研究・研修東京センター「認知症と服薬管理」
- 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター「高齢者の服薬管理の工夫」

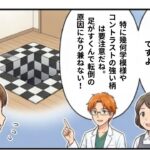

コメント