医療や介護の現場は、日々「人」と「感情」に向き合う仕事です。
患者や利用者の不安、家族の苛立ち、スタッフ間のすれ違い——。どれも無視できず、そして正面から受け止めざるを得ない状況が続きます。
その結果、夜になっても心が落ち着かず、疲れ果てたまま眠りにつく。翌朝には前日の感情を持ち越して出勤……そんな経験はありませんか?
そんな日々を変えるために、おすすめしたいのが「感情ログ」を書く習慣です。
感情ログとは何か?
「感情ログ」とは、その日の感情の動きを言語化して記録する習慣です。
目的は単なる「愚痴」ではなく、感情を客観視して、整えること。
以下の5つのステップで書きます:
- ✅ 何があったか(事実)
- ✅ その時どう感じたか(感情)
- ✅ どんな思考をしたか(思考)
- ✅ 本当はどうしたかったのか(欲求)
- ✅ 今、自分にできることは何か(対処)
ステップ1:まず“事実”だけを書く
最初は「何が起こったか?」という“事実”だけを記録します。
午後、◯◯さん(スタッフ)に指示を出したが、「今忙しいんで」と言われた。
感情や評価を入れず、なるべく客観的に書きましょう。
ステップ2:“感情”をそのまま書く
次に、その時に湧いた感情を言葉にします。
- 悲しい
- ムッとした
- 悔しい
- 情けない
- 腹立たしい
ここでは「良い」「悪い」で評価しないことが大切です。
ステップ3:“思考”を見つめる
その感情の裏にある「思考パターン」を探ります。
薬局長としてバカにされた気がした。
この程度の仕事もできないのかと思われたくない。
ステップ4:“本当の欲求”に気づく
感情の奥には「本当はこうしてほしかった」という欲求があります。
- ちゃんと話を聞いてほしかった
- 自分を尊重してほしかった
- 指示を受け入れてほしかった
ステップ5:“今できること”を考える
最後に、できること・行動に落とし込みます。
彼女が忙しそうだったことに気づけなかった。
次回は「今、少し話せる?」と聞いてから話そう。
感情を“色”でラベリングすると書きやすい
感情を3色で分類すると、書きやすくなります。
- 🔴怒り系:イライラ、悔しい、腹が立つ
- 🔵悲しみ系:寂しい、不安、無力感
- 🟢喜び系:うれしい、安心、感謝
愚痴ではなく、整えるための“ログ”
「感情ログ」は、ただの吐き出しではありません。
愚痴は一時的なガス抜きにはなりますが、感情を“消化”することはできません。
逆に、繰り返し話すことで感情が強化されてしまうこともあります。
感情ログは、感情を「観察」し、「理解」し、「手放す」プロセスです。
医療現場での感情ログの意義
医療・薬局現場では「感情を抑えることがプロ意識」と思われがちです。
しかし、抑え込んだ感情は蓄積し、バーンアウトのリスクになります。
自分の感情を丁寧に扱うことが、プロとしての持続可能な働き方に繋がるのです。
まとめ:感情を“整える力”を持とう
感情ログは、感情をコントロールするためのツールではありません。
感情に「気づき」「認め」「向き合う」ための習慣です。
5分でもいいので、今日から始めてみませんか?
それが、心の安定と、信頼されるマネジメント力を育む第一歩になるはずです。
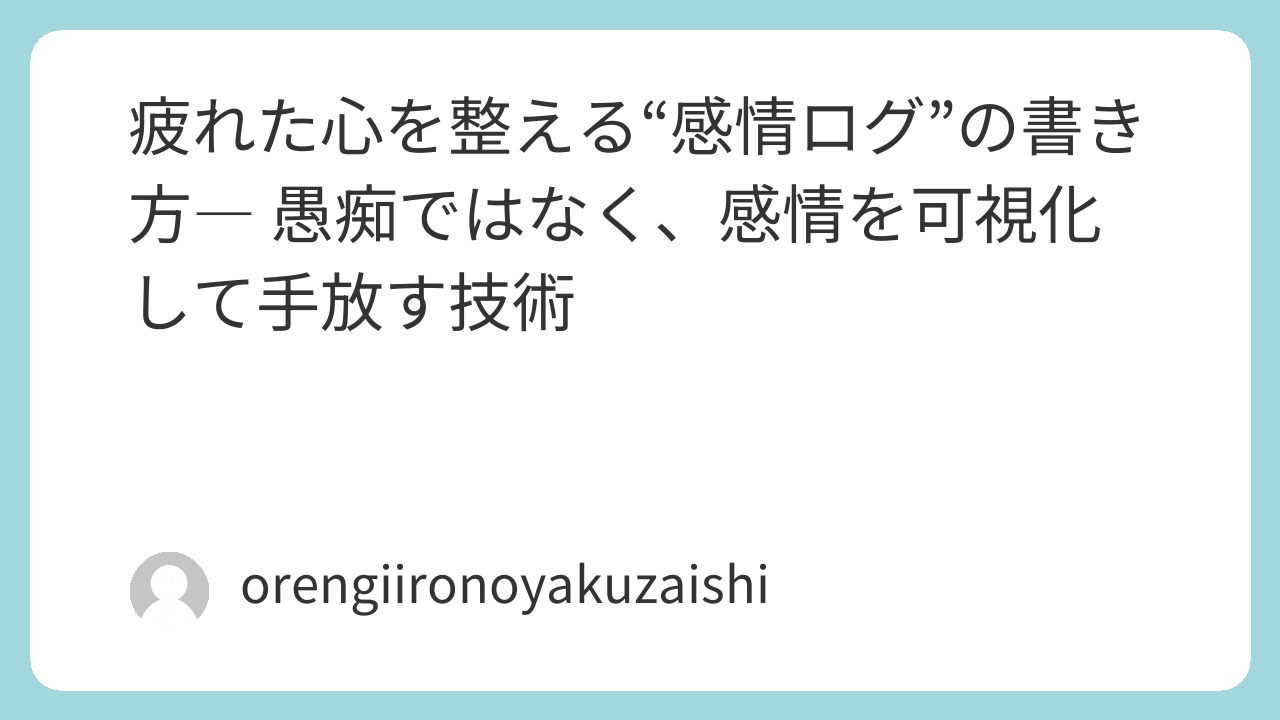


コメント