はじめに
認知症は、単なる「もの忘れ」とは異なります。加齢による物忘れは出来事の一部を忘れるだけで、ヒントがあれば思い出せますが、認知症の場合は出来事そのものを忘れ、ヒントを与えても思い出せません。
日本では高齢化の進行とともに、65歳以上の約7人に1人が認知症と推計されています(厚生労働省推計、2020年時点)。
今回は、家族が日常生活の中で気づきやすい「認知症の初期サイン10選」を具体例とともに紹介します。
1. 直近の出来事を忘れる

- 特徴:数時間前や昨日の出来事を忘れ、同じ質問を繰り返す。
- 例:「さっき昼ごはん食べたの?」と何度も聞く。テレビで同じニュースを見て「初めて知った」と話す。
- ポイント:加齢による物忘れは「何を食べたか」など一部を忘れますが、認知症では「食べた事実」自体を忘れます。
2. 慣れた場所で迷う
- 特徴:長年住んでいる自宅近くや行き慣れた商店で道に迷う。
- 例:散歩中に帰り道がわからなくなる。駅やバス停で、自宅の方向が思い出せない。
- ポイント:空間認知機能の低下で方向感覚や位置関係が把握できなくなります。
3. 言葉がうまく出てこない
- 特徴:物や人の名前が思い出せず「あれ」「それ」で済ませることが増える。
- 例:「あの四角いやつ取ってくれ」(本当はテレビのリモコン)。長年の友人の名前を突然忘れてしまう。
- ポイント:語想起障害と呼ばれ、アルツハイマー型認知症の初期に多い症状です。
4. 物の置き忘れやしまい忘れが増える
- 特徴:財布や鍵、メガネなどを置いた場所を思い出せない。
- 例:冷蔵庫に財布を入れてしまう。洗濯機の中に携帯電話を入れてしまう。
- ポイント:場所を忘れるだけでなく、場違いな場所に置くケースが目立ちます。
5. 計算やお金の管理が難しくなる

- 特徴:簡単な計算に時間がかかる。公共料金の支払い方法を忘れる。
- 例1:おつりの計算ができない、同じ請求書を何度も払おうとする。財布に小銭が大量にたまり、なんでも1万円札で支払おうとする。
- ポイント:数字や順序立てる作業が苦手になり、家計や支払いが混乱します。
6. 予定や約束を忘れる
- 特徴:カレンダーに書いても予定そのものを忘れる。
- 例:通院日を忘れて病院から連絡が来る。家族との食事会を約束したことを覚えていない。
- ポイント:メモを見ても思い出せない場合は要注意です。
7. 判断力が低下する
- 特徴:いつもと違う金銭的判断や行動をする。
- 例:必要ない高額商品を突然購入する。詐欺電話に引っかかる。同じ商品を何度も買い、冷蔵庫が同じものでいっぱいになる。郵便ポストの郵便物が長期間たまっている。
- ポイント:社会的判断や危機管理能力が低下し、生活の安全が脅かされます。
8. 服装や身だしなみへの関心が薄れる
- 特徴:季節や天気に合わない服装をする。
- 例:真夏に厚手のセーターを着て外出する。片方の靴下だけ履いて出かける。
- ポイント:衣服選びや身だしなみへの意識が低下します。
9. 趣味や交流への興味が薄れる
- 特徴:これまで楽しんでいた趣味や活動に参加しなくなる。
- 例1:囲碁仲間との集まりに行かなくなる。長年参加していた地域行事やボランティアに姿を見せなくなる。
- ポイント:意欲低下やうつ症状が背景にある場合もあります。
10. 感情の起伏が激しくなる
- 特徴:感情のコントロールが難しくなる。
- 例:些細なことで怒鳴る、突然泣く。笑うべき場面で笑わない、逆に不自然に笑い続ける。
- ポイント:脳の変化によって感情表現が不安定になります。
早期発見のための家族の視点

認知症の初期は本人の自覚が薄く、「年のせい」で済まされがちです。
複数のサインが頻繁に見られるようになったら、早期受診が重要です。
医療機関で行われる主な診断
- 簡易認知機能検査(長谷川式スケール、MMSEなど)
- 血液検査・画像検査(脳腫瘍や甲状腺機能低下症など他の原因除外)
- 専門医による問診・行動観察
まとめ
今回紹介した「10の初期サイン」は、家族が変化に気づくためのヒントです。
「以前と違う」と感じたら早めに専門医へ相談することが、本人の尊厳と生活の質を守る第一歩となります。地域包括支援センターに相談してもいいと思います。市役所や介護施設に併設されていることが多いです。
早期診断・早期対応によって、認知症の進行を遅らせ、より良い生活を維持する可能性が高まります。
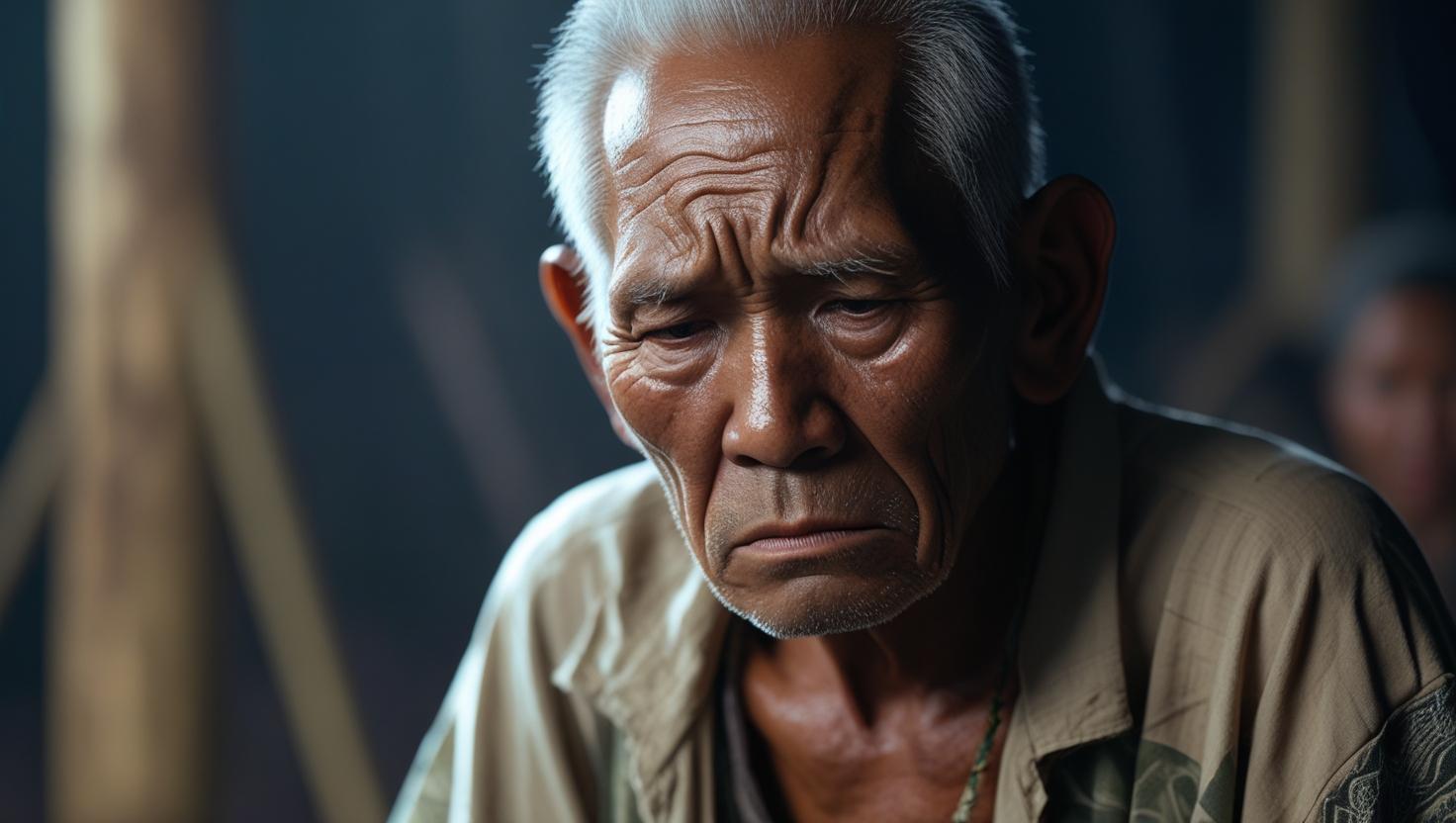


コメント