はじめに
「最近、母が同じことを何度も聞いてくるんです。最初は年齢のせいだろうと思っていたのですが、冷蔵庫に食材を入れ忘れたり、財布をどこに置いたか忘れたりすることが増えて…。もしかして認知症なのではと不安になりました」
こうした声は、介護現場や家族会でもよく耳にします。私自身、薬剤師として在宅訪問の場でご家族から同じ相談を何度も受けてきました。アルツハイマー型認知症は、日本で最も多い認知症のタイプであり、進行性の病気です。初期の段階では「うっかり」「物忘れ」と見過ごされることもありますが、進行すると生活全体に支障をきたしていきます。
この記事では、アルツハイマー型認知症の特徴、初期症状、原因、進行の過程を、介護関係者やご家族に向けてわかりやすく解説します。正しい知識を持つことで、早期の気づきや適切な対応につながります。
1. アルツハイマー型認知症とは?
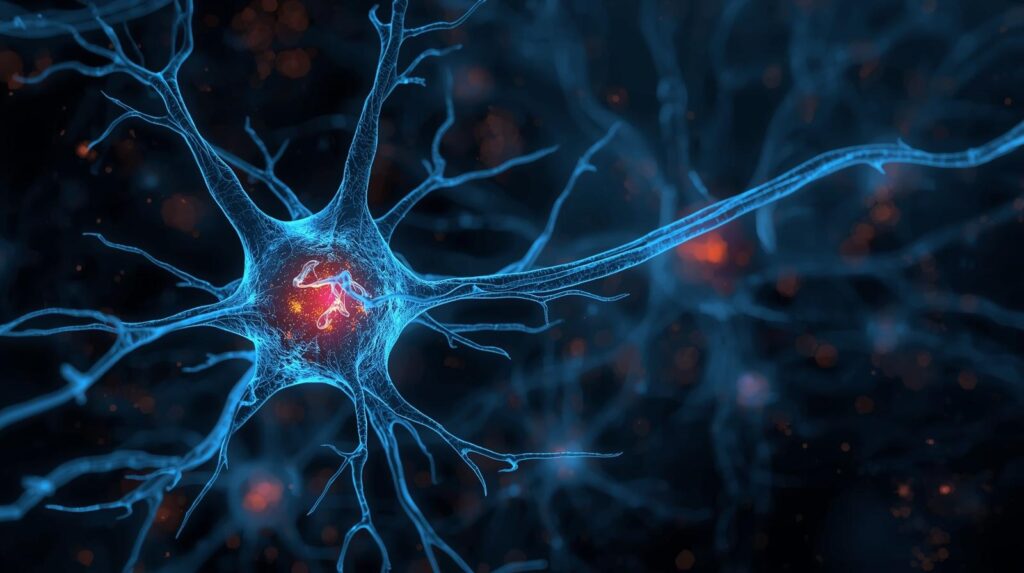
アルツハイマー型認知症は、脳の神経細胞が徐々に壊れていくことで記憶力や判断力が低下し、日常生活に支障をきたす病気です。認知症全体の中で最も多く、日本における認知症の約6割を占めるとされています。
脳内では、「アミロイドβ」という異常なたんぱく質が蓄積し、さらに「タウたんぱく」が神経細胞を壊すことで脳の萎縮が進みます。この変化は数十年単位で進行し、目に見える症状として表れる頃には、すでに脳の変化が広範囲に進んでいることも少なくありません。
2. 初期症状の特徴
2-1. 物忘れの質が違う
年齢による「物忘れ」と、認知症による「記憶障害」は性質が異なります。
- 加齢による物忘れ:体験した出来事の一部を忘れる(例:旅行先で食べた料理の名前を忘れる)。
- 認知症による物忘れ:体験そのものを忘れる(例:旅行へ行ったこと自体を忘れる)。
家族から「同じ質問を繰り返す」「約束したことを完全に忘れる」といった相談が多いのは、この違いによります。
2-2. 時間や場所がわからなくなる
「今日は何日?」「今どこにいるの?」といった質問が増えるのも初期のサインです。カレンダーや時計が身近にあっても把握できなくなることがあります。
2-3. 判断力や理解力の低下
会話のテンポについていけない、人の話がわからない、案内板を見ても理解できない、鉛筆を渡されても、どうしていいかわからない、鉛筆を鉛筆と認識できない、鉛筆という言葉が出てこないなど、失行、失認、失語などもあります。
2‐4. 今までできたことが出来なくなる
服を着替えられない、電車に乗り方がわからない、料理や掃除ができない、車の運転ができない、
箸の使い方やトイレの仕方、お風呂の入り方、など今まで当たりまえにやっていたことが出来なくなります。
2-5. 興味や意欲の低下
趣味に手をつけなくなる、人付き合いを避ける、テレビや新聞を見ても内容を理解できないなど、意欲の低下が目立ち始めます。
3. アルツハイマー型認知症の原因
現在の医学では、アルツハイマー型認知症の原因は完全には解明されていませんが、主に以下の要因が関係していると考えられています。
- アミロイドβたんぱくの蓄積:神経細胞の間に沈着し、細胞を障害する。
- タウたんぱくの異常:神経細胞の中で構造を壊し、脳の萎縮を進める。
- 遺伝要因:ごく一部は遺伝的要因で発症することもある。
- 生活習慣病との関連:高血圧、糖尿病、脂質異常症などの影響。
- 加齢:最大のリスク要因。
「なぜ自分の家族がアルツハイマー型認知症になったのか」と悩まれるご家族は多いですが、現時点では一つの原因に限定できるものではありません。むしろ複数の要因が重なって発症すると考えられています。
4. 病気の進行と症状の変化

アルツハイマー型認知症は進行性の病気です。大きく「軽度」「中等度」「重度」の段階に分けて理解すると、ご家族や介護者も対応がしやすくなります。
4-1. 軽度(初期)
- 物忘れが増える
- 日付や場所がわからなくなる
- 慣れた道でも迷うことがある
- 趣味や会話への興味が薄れる
この段階では、周囲が「少し変だな」と気づき始める時期です。
4-2. 中等度(中期)
- 家事や買い物ができなくなる
- 服の着脱が一人では難しくなる
- 妄想(物を盗まれたと思い込むなど)が現れる
- 昼夜逆転の生活になる
- トイレの失敗が増える
介護の負担が大きくなり、ご家族の心身のケアも重要となる時期です。
4-3. 重度(後期)
- 会話がほとんどできなくなる
- 食事や排泄など、生活の全てに介助が必要になる
- 寝たきりになることもある
ここまで進むと、介護施設や医療機関との連携が欠かせません。
5. 家族や介護者が知っておくべきこと

5-1. 早期受診の大切さ
「年のせい」と思って放置すると、治療や介護の準備が遅れてしまいます。もの忘れが気になるときは、かかりつけ医や専門医に相談することが大切です。
5-2. 薬物療法と非薬物療法
現在、日本ではアルツハイマー型認知症に対して複数の薬が承認されています。ただし、進行を完全に止める薬はなく、症状の進行を遅らせることが目的です。あわせて、生活リハビリや認知症カフェ、家族会などの非薬物的支援も有効です。
5-3. 介護者の負担軽減
介護保険サービスを利用し、デイサービスや訪問介護、ショートステイを取り入れることで、家族の負担を軽減できます。「自分ひとりで抱え込まないこと」が何より大切です。
6. まとめ
アルツハイマー型認知症は、日本で最も多い認知症であり、進行性の病気です。初期の段階では「物忘れ」と混同されやすいですが、記憶の質の違いや判断力の低下などに早く気づくことが大切です。
家族や介護者にとっては不安が大きい病気ですが、正しい知識を持ち、医療や介護サービスを活用することで、本人と家族の生活の質を守ることができます。
出典
- 厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」
- 日本老年精神医学会「認知症疾患治療ガイドライン」
- 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター
- アルツハイマー病国際協会(Alzheimer’s Disease International)



コメント