(司法書士が解説)
1. はじめに
親が高齢になってくると、心配になるのが「もし認知症になったら」という将来のこと。
認知症は誰にでも起こりうる病気で、厚生労働省の推計によると、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると言われています。
実際に発症してから対策を取ろうとすると、本人の意思確認が難しくなったり、財産の手続きが進まなくなったりすることが少なくありません。
司法書士の立場から見ると、「早めの準備」ができているご家庭ほど、混乱やトラブルを最小限に抑えられます。
ここでは、認知症になる前に家族で準備しておくべきことを8つに絞って解説します。
2. 1つ目:家族で将来の希望を話し合う
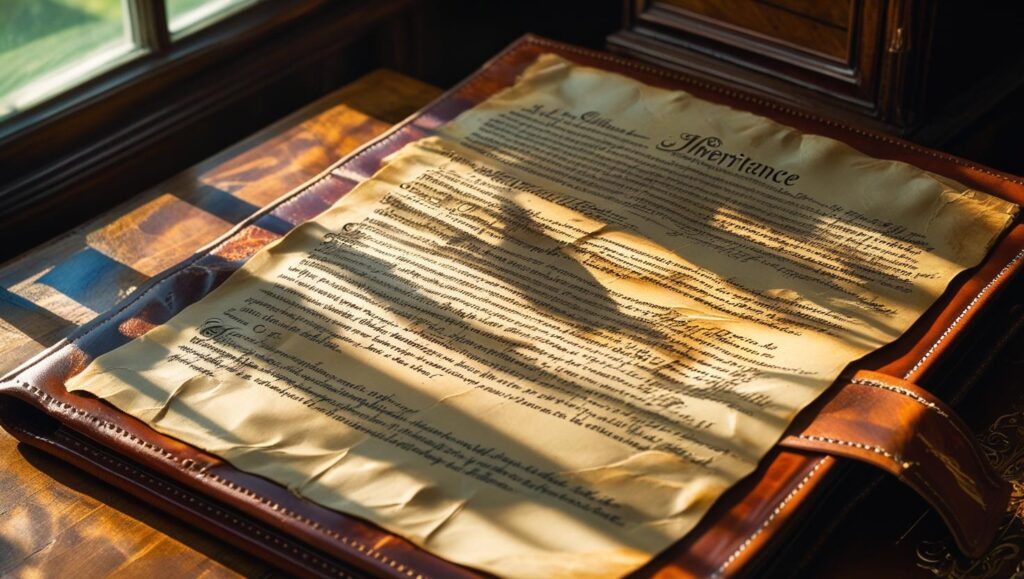
制度や契約より先に大切なのは、本人の意思を知ることです。
- どこで暮らしたいか(自宅、施設、子どもの家など)
- 誰に財産管理を任せたいか
- 延命治療や介護サービスの希望
これらは、元気なうちに聞いておかないと後から確認できません。
話しづらいテーマですが、「いざというとき困らないために」という前置きがあると話しやすくなります。
3. 2つ目:財産や契約の棚卸し
認知症になると、自分名義の財産や契約の管理が難しくなります。
事前に以下を整理しておくとスムーズです。
- 預貯金口座の一覧(銀行名・支店・口座種別)
- 有価証券や保険証券
- 不動産(土地・建物の権利証や登記事項証明書)
- 借入やローンの有無
- クレジットカードやサブスク契約
ポイントは、家族が探さなくても分かる状態にしておくことです。
4. 3つ目:任意後見契約を検討する
判断能力があるうちに、将来の財産管理や契約手続きを信頼できる人に任せる契約です。
- 契約方法:公証役場で公正証書として作成
- 後見監督人:家庭裁判所が選任
- 開始時期:本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が後見開始を決定したとき
任意後見は、「誰に」「どの範囲で」任せるかを事前に決められるのが大きな利点です。
5. 4つ目:財産管理契約の活用
任意後見と似ていますが、こちらは契約を結んだ直後から代理権を発動できるのが特徴。
- 判断能力が十分にある状態でも利用可能
- 日常的な金銭管理や支払い代行ができる
- 高齢者施設への入居手続きなどもサポート可能
例えば「まだ認知症ではないが、銀行や役所に行くのが大変」という場合にも使えます。
6. 5つ目:家族信託の検討
信頼できる家族に財産を託し、本人や家族のために管理・運用してもらう制度です。
- 任意後見ではできない柔軟な財産承継設計が可能
- 将来の相続対策と併せて利用できる
- 不動産の管理・処分をスムーズに行える
家族信託は制度設計が複雑なため、必ず専門職(司法書士・弁護士)に相談しましょう。
7. 6つ目:医療・介護の意思表示(ACP)

「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」とは、将来の医療や介護について事前に話し合い、記録しておくことです。
- 延命治療の希望
- 入院か在宅かの希望
- 誰に判断を託すか(代理人)
書面化する場合は「事前指示書(リビングウィル)」として残すこともできます。
8. 7つ目:重要書類の保管方法を決める
認知症発症後、書類が見つからないことは珍しくありません。
- 公正証書や契約書
- 保険証券や年金手帳
- 登記関係書類
- 印鑑と印鑑登録証
これらは耐火金庫や信頼できる家族・専門職の事務所に預ける方法があります。
9. 8つ目:早めの専門職相談

認知症に関する準備は、制度や契約が複雑に絡み合います。
- 司法書士:任意後見・家族信託・財産管理契約
- 弁護士:紛争やトラブルへの対応
- 税理士:相続税・贈与税の試算
- 社会福祉士:介護制度利用の支援
複数の専門職と連携することで、抜け漏れのない準備が可能になります。
10. まとめ
親が認知症になる前に準備しておくことは、家族の負担を軽くし、本人の希望を叶えるために不可欠です。
今回紹介した8つの準備
- 家族で将来の希望を話し合う
- 財産や契約の棚卸し
- 任意後見契約の検討
- 財産管理契約の活用
- 家族信託の検討
- 医療・介護の意思表示(ACP)
- 重要書類の保管方法を決める
- 早めの専門職相談
いずれも「まだ元気なうち」に始めることがポイントです。
司法書士としても、早めの相談がトラブル防止の最大の秘訣だと実感しています



コメント