投稿日:2025年7月27日|著者:オレンジ色の薬剤師
薬局で起こりがちな「やらない」問題
ある薬局で、午前中に届いた在宅患者用の処方箋が、夕方になっても準備されていませんでした。
薬局長が確認すると、「誰かがやると思っていた」「声をかけづらかった」という返答が返ってきます。
「なんでやらないの?」という言葉が喉元まで出かかるこのような場面。
しかし、そこで責めるような態度を取ってしまうと、部下はさらに委縮し、状況は悪化していきます。
アドラー心理学の「目的論」とは?
アドラー心理学は、「人は原因ではなく目的によって行動している」と捉えます。
「やらなかった」のではなく、「やらないことで守っているものがある」と考えるのです。
上記の事例でも、「怒られたくない」「責任を背負いたくない」「人間関係の摩擦を避けたい」といった“目的”が、行動の裏側に存在していた可能性があります。
「原因論」の落とし穴
多くのマネージャーは、部下が行動しない理由を「性格」「過去の経験」「能力の不足」など“原因”で説明しがちです。
しかし、こうした見方では相手を固定し、成長の可能性を閉ざしてしまいます。
アドラーは「人は常に変われる存在」であると捉え、未来志向のコミュニケーションを重視します。
重要なのは、「どうすれば行動を変えられるか?」という問いを立て直すことなのです。
目的論的マネジメントの実践方法

①「何のために?」と目的に注目する
行動の目的に意識を向けることで、「責める」ではなく「理解する」姿勢が育まれます。
例:報告しない部下に「なぜ言わなかった?」ではなく、「何か不安があったのかな?」と尋ねる。
②「なぜ」より「どうすれば?」を使う
ここで重要なのが、問いの立て方を変えることです。
管理者自身の「問いの立て方」が変わることで、相手の受け取り方も変わります。
「なぜできないの?」から「どうすればできる?」への転換。
これは、責めるマネジメントから、力を与えるマネジメントへの転換でもあります。
③小さな成功を一緒に作る
「誰も声をかけなかった」という事例では、次から「午前中の在宅処方箋は◯時までに◯◯さんがチェック」と役割分担を具体化し、小さな成功体験を共有していくことが重要です。
問いの立て方を変えると、関係性が変わる
部下のやる気や行動を引き出す鍵は、上司の問いかけにあります。
「なぜできないのか?」という詰問ではなく、「どうすれば動きやすい?」「どんな工夫ができる?」という前向きな問いが、信頼と自立を育てます。
このような問いかけを重ねることで、部下自身が目的に気づき、主体的に動き出す環境が生まれていくのです。
まとめ|目的に目を向ける力がチームを変える

「やらない」行動の裏には、必ず「目的」がある。
その目的を見抜き、力づける問いかけができるリーダーこそが、信頼される管理者です。
「なんでやらないの?」という過去志向の問いから、「どうすればできる?」という未来志向の問いへ。
それは、部下を責めるのではなく、共に成長するための一歩です。
薬局というチームで働く私たちにとって、目的論的な視点は、スタッフの行動だけでなく、マネジメントそのものを優しく、強く変えてくれる武器になります。
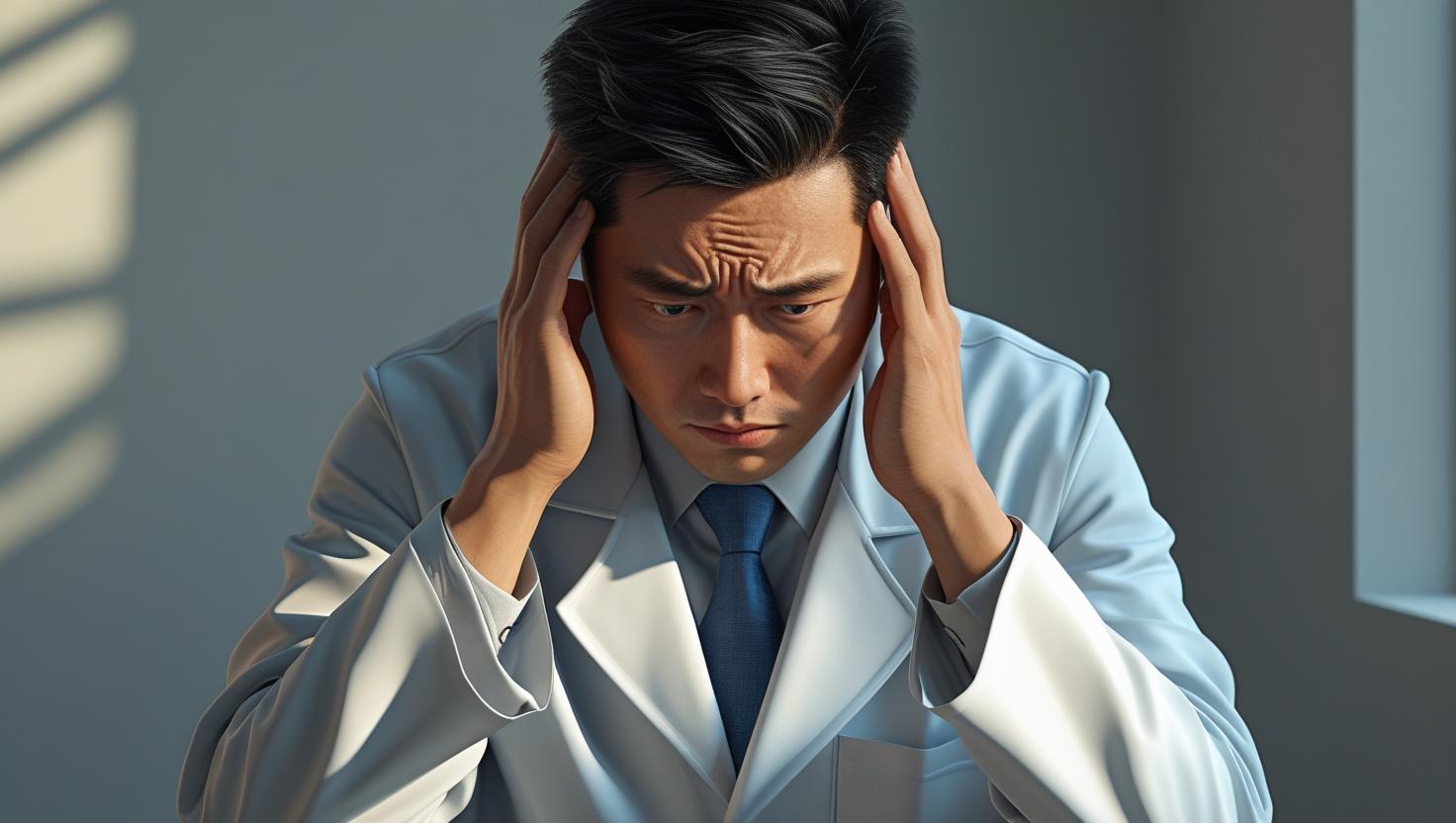


コメント